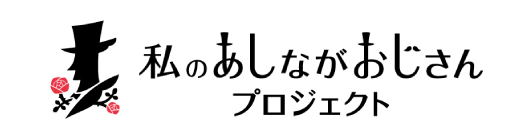Essay
エッセイ・連載
第28回 私たちに委ねられた任務は、まちに「森」をつくること-「公共の概念」が失速する時代と向き合って。
2021- 「人間の家」の劇場経営をナビゲートする。
2025 年 12 月 13 日 (土)
劇場経営・文化政策アナリスト 早稲田大学文化推進部参与 衛 紀生
「森と魚貝の連鎖」を公共劇場のメタファーとして捉える。
「牡蠣の森を慕う会(現NPO法人森は海の恋人)」の理事長だった故畠山重篤さんのドキュメンタリーを偶然に見ることが出来ました。気仙沼の舞根湾での畠山重篤さんの海の再生活動は、東日本大震災の時に、これも偶然でしたが、オンエアされた時に、漁民をたばねて広葉樹の植林活動を行っているその生き方に深く共感をして、その後の活動にも関心を持ち続けていました。『芸術文化行政と地域社会』を97年に上梓した際、序章に「カキの森の文化政策」とのタイトルをつけて、豊かで健やかな地域社会を創生させるために社会を支援する文化拠点=劇場ホールをカキの森のようにつくらなければならない、と記しました。この暗示を受けたのもNHKのドキュメンタリーでした。北海道・厚岸の牡蠣漁師が山に登って木を植えるという水産海洋学の奈須敬二先生の著作から想を得たものでした。それとほぼ同時期に、開発による森林伐採が鰊の群来を幻にしてしまった、という内容のテレビ番組も見ました。秋田の海から鰰が消えたのも、河川上流での森林伐採の疑いがあるという。道東の厚岸の牡蠣は、急激な漁獲量の落込みを漁民らの植林事業によって復活したのだという。JALのキャンペーンにコピーライターとして参画した折に、木造の厚岸の小さな駅舎で売っていた「かきめし弁当」は、生醤油で味々と煮しめた飾り気のないもので、いかにもこの町の人々の生活に根付いていて厚岸湖の牡蠣を誇りと思っていることが伝わってくる一品でした。「雨が森に降り、森林の蓄えていた栄養分が伏流水に溶け込んで川となり、流域をうるおし、海に流れ込んで海藻や植物プランクトンの生長を促し、豊かな魚介類を育てる」という「森と魚貝の連鎖」は、奈須敬二先生が力説するところですが、私はその番組から少なからずショックを受けました。私たちの生きている時代が未来を消し去るようにしかないのだとしたら、これはいたたまれないと思ったのです。
『芸術文化行政と地域社会』は、演劇雑誌『テアトロ』におよそ2年半にわたって連載していた「50―50」(フィフティ・フィフティ)の一部を採録、大幅加筆して、ほほ書下ろしに近い著作なのですが、厚岸の牡蠣漁師の番組がオンエアされたのが何年だったのか正確には記憶していません。93年に長崎の障害児たちの「のこのこ劇団」と出会って演劇の社会的価値が社会政策立案に重要な役割を持っていることを教えられ、翌年に受益と負担の圧倒的アンバランスこそが「ハコモノ批判」と「税金のムダづかい」の発火点であり、それを克服する方策としてま翌年に阪神淡路大震災が起きて、一年がかりで組成した神戸シアターワークスの活動の実践知から、「まちは人と人の関係性の集積」との啓示を受けたのですから、奈須敬二先生の著作に触れたのも、厚岸のドキュメンタリーに衝撃を受けたのも、おそらく94年から96年あたりではないかと漠然と推測しています。これも『芸術文化行政と地域社会』を上梓した後と記憶していますが、NHKドキュメンタリー番組で、オーストラリアの砂漠地帯に延々と流れる川が空撮で写されていて、その流域の両岸に沿って緑の樹木が自生している映像を見て、奈須先生の持論の確かさが腑に落ちたことも思い出します。この私のカキの森の劇場哲学は、アーラで館長職を13年間務めて現場の実践知の幾重もの集積と、紆余曲折の深掘りの試行錯誤の堂々巡りから多くの事を学びながら、『芸術文化行政と地域社会』を上梓した翌年にウエストヨークシャー・プレイハウス(WYP)を訪れて、当時の日本ではおよそ考えられない、想像を絶する個々人が受け容れられていることからくる「くつろいだ空気」に充たされている雰囲気からマーケティングの本質である継続的に支持されて長期的に利益をもたらす「生涯価値」を実現している「顧客の創造」を劇場という業態で成立させているとの確信から、エシカル・プラットフォームとしてのWYPの公益性(Public)による社会的存在価値とだったのではないかとのぼんやりした解の輪郭にたどりつけた現在に至っても、私は奈須先生の「森と流域と豊饒の海」のつながりに公共文化施設の隠喩は揺らぎないものとしてあります。
「公益と公共の失速」する時代に、Publicの意味をあらためて考える。
上記の「Public」について、最近とても違和感を覚える出来事がありました。設置自治体である愛知県が「愛知芸術文化センターの建物管理及び芸術劇場の運営(以下「愛知県芸術劇場等運営等事業」という)について、公共施設等運営権(コンセッション)方式を導入することとしており、公募型プロポーザル方式による事業者の募集・選定手続を進めてきました」とのコメントを発して、2025年9月に、愛知芸術文化センターの建物の管理および芸術劇場の運営を民間に任せる「コンセッション」方式の導入にあたり、中日新聞社を代表企業とする企業共同体「中日アライアンスグループ」が優先交渉権者に選ばれたというニュースです。私はこの出来事を、行政が「公益性と公共」の概念の縛りから遁れようとしているのではないか、その責任(主として財政負担)に耐えかねて営利目的の施設に転換したのではないかという疑念を拭えないでいるのです。仮にそうであるならば、90年代のホール建設ラッシュはまぎれもなく「政府の失敗」であり、しかも「興行」の成立する人口規模に立地が限定されてしまうことになります。私は文化芸術へのアクセシビリティは、憲法第13条の「すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」を根拠としていると90年代から考えていますし、文化芸術の振興に関する基本的な方針(2011年2月8日閣議決定)で文言化した社会包摂機能(共生社会実現への戦術的有用性)は、文化芸術の社会政策への汎用性を担保した成果と言い続けてきました。公共劇場及びホールの「公共」とは、その社会的機能を包含してこその「公共」なのであり、興行収益のみを目的とする施設は、必要条件は充たしているものの十分条件には至っていないと明断できます。したがって、前述したWYPの「くつろいだ空気の賑わい」は、幸福追求権の保障された時空に充たされていたに違いないと臆断するのです。セグリマンのポジィティブ心理学の知見で吟味すれば、それは「感情的で瞬間しか続かない、スパンの短いHappiness」ではなく、「身体的、精神的、社会的に良好で満たされた持続的な状態であるWell-being」と評価すべき、いわば顧客満足度の高さではなく顧客幸福度に充たされた時空を享受する市民の姿だったのではないかと想起するのです。
そのようなWYPは、しかしながら公立の施設ではありません。チャリティ格を有する(米国でのNPO法人格)有限会社です。チャリティとは、Charity Commission(慈善事業監督委員会)の審査を受けてRegistered charity(登録チャリティ)になることで公益性が認められなければなりません。これによって英国芸術評議会をはじめとする公的機関からの助成が得られるようになります。それにはいくつかの条件があり、
①公共性を有しており、教育を目的として、利益を追求しないこと。
②無給の理事会の設置。
➂政治的ロビー活動はしない。
④大きな利益は出さない。
の条件を満たして登録チャリティ格を得ると、①助成金が受けやすくなる、②税金の減免、➂社会的信用度が増す、④民間からのスポンサードを得やすくなる、という経営上のアドバンテージが生じることになります。そのような基盤を創ったのは、大戦後の労働党政権の首相であるクレメント・アトリーです。第二次世界大戦後の荒廃した国土と国民の精神を健全化に向かわせ、すべての国民の「Well-Being」(幸福・福利)のためにクレメント・アトリー政権が打ち出した二大政策のひとつに、あまりに有名な「揺り籠から墓場まで」と言われるようになる社会福祉政策があります。これが英国の保健医療機関であるナショナル・ヘルスサービスの設立へとつながるのですが、いまひとつは、のちの英国芸術評議会の設立を準備する「多くの人々が参加できるように文化芸術の幅(対象)を拡げること」と「社会の問題解決のための文化芸術の社会的役割を果たすこと」の2つの文化政策のパラダイムをアトリーが提言します。前者は一部の特権階級や愛好家の独占物にしないことが公的資金導入の条件であり、しかも社会的・階級的矛盾によって生じる社会課題を解決に向かわせるために文化芸術及び文化施設を活用する積極的福祉政策と社会政策の展開を想定したものと言えます。アトリーは、公的資金による文化支援が国民的合意を形成し、可能となるための条件を明確に提示したのです。ここに至って、芸術団体や劇場ホールなどの文化施設への公的支援を初めて「投資」と言い切ることが出来るのです。 「コストからインベストメントへ(負担から投資へ)」という経済的支援の考え方の大転換が提示されます。日本はアトリーに遅れること60数年、第三次基本方針で「従来、社会的費用として捉える向きもあった文化芸術への公的支援に関する考え方を転換し、社会的必要性に基づく戦略的な投資と捉え直す。 そして、成熟社会における新たな成長分野として潜在力を喚起するとともに、社会関係資本の増大を図る観点から、公共政策としての位置付けを明確化する」と初めて明示されます。
「第2期文化芸術推進計画(中間報告)」にあるような「マーケットイン」という不適切な用語を盛り込んだ不定見、不見識きわまる第20期文化政策部会は、前述の英国におけるクレメント・アトリーの業績、そして第三次基本方針の「コストからインベストメント」への大転換、後述する米国の「リージョナルシアター運動」などの新時代を切りひらいた歴史的なエポックメイキングをどう評価して、心得ているのだろうか。リージョナルシアター運動を担った若手演劇人やニューヨーク大学の演劇科の学生たちの主張が、まさにブロードウエイの「マーケットイン」の価値観で創造される舞台にあったのです。先の愛知県のコンセッション方式への転換が、文化政策の基本スキームである組織や個人の強みをベースとして作品創造をする「プロダクトアウト」ではなく、市場からの求めに応じる「マーケットイン」に180度転換したのではないかとの疑いが頭から離れられません。
芸術文化の高付加価値化を生むためのマーケティング・イノベーションを。
第二期「文化芸術推進計画」の策定に向けた文化政策部会の中間報告にある「マーケットイン」は、市場におもねる或いは追従するとの意味がマーケティング分野ではあって、文化芸術の創造主体に向けて発出するにはかなりの偏りがあるのではないかとの疑義を禁じ得なのです。宮田亮平前文化庁長官から京都でのカンファレンスの際に「稼ぐ文化」を聞いた時の違和感と抵抗感は忘れられません。「稼ぐ文化」が、芸術文化の芸術的価値と市場的価値の混淆、あるいは混同という誤った認識によって、芸術文化機関に経済的自立、自走化を促して、国の財政負担を軽減化するかのような「エコシステム」という言辞を使用して、いかにも正当な手段のような言説を装っていることに私は疑義を挟まざるを得ません。「稼ぐ文化」の背景には、2016年6月に閣議決定した「骨太の方針2017」の「稼ぐ文化への展開」を記載して「文化による国家ブランド戦略の構築と文化産業の経済規模(文化GDP)の拡大に向け取組を推進する」としていて、そのための「文化庁の機能強化」だとも言っています。それに付随して発出された「未来投資戦略2017」には、文化GDPを2025年までにGDP比3パーセント程度、18兆円までに拡大することが記されています。ちなみに前年の2015年は8.8兆円で2014年は8.7兆円と併記されています。また具体的施策として「文化芸術・観光・産業が一体となり新たな価値を創出する『稼ぐ文化』への展開を推進する」と文化芸術とインバウンドを視野に観光との施策との連携が提言されています。私も90年代後半に「北海道劇場計画」に主査として関わっていた折に、候補地が札幌駅前の高度利用地区だったために1500キャパの大劇場から600席の中劇場、100席の2つの小劇場と計画していたのですが、大劇場は、当時はそれほど多くはなかったインバウンド向けにミュージカル専用と構想していたことがあります。「骨太の方針2017」はアベノミクス成長戦略の一環として協議されて公示されただけに、必ずしも国民のWell-beingにはつながらないというGDP指標の創案者クズネッツの積み残した検討課題のあるGDPへの検証なく、ひたすらGDPを積み増すことだけにわき目も振らずに一瀉千里の感は否めません。文化庁は、2018年年4月に「稼ぐ文化」の立場から『アート市場の活性化に向けて』という文書を出しました。これに対して、全国388の美術館で構成する全国美術館会議は、「美術館が自ら直接的に市場への関与を目的とした活動を行うべきではない」、「美術作品を良好な状態で保持、公開し、次世代へと伝えることが美術館に課せられた本来的な役割であり、収集に当たっては投資的な目的とは明確な一線を画さなければならない」との声明を出しました。同じ年に、山本幸三・地方創生相が「地方創生とは稼ぐこと」と定義して、観光振興をめぐり「一番のがんは文化学芸員と言われる人たちだ。観光マインドが全くない。一掃しなければ駄目だ」という不見識な発言をしたことを記憶している向きもあろうかと思います。オークション会場と美術館は、まったく異なった機能によって運営されていることは自明です。学芸員とアート投資をアドバイスするアートディーラーとは、まったく異なる役割を持っています。これを同一視することは、美術品の芸術的価値を貶めることになるのは必定です。産業特性と職能を勘案すべきであるにもかかわらず、経済成長を絶対価値として、遮二無二に政権への忖度を働かせているとしか思えない出来事でした。あわせて、「稼ぐ文化」発言をした宮田前文化庁長官は、東京藝術大学の学長を務めた人物であり、ボーモルとボウエンによる古典的名著『舞台芸術 芸術と経済のジレンマ』が指摘している「コスト病」に対する知見は常識的に持っているにもかかわらず、オペラやオーケストラという労働集約型の舞台芸術は東京藝大の守備範囲であるにもかかわらず、それに対しての発言がないのはいかがなものか。「GDP」は、大恐慌の時のフーバー政権の依頼で経済学者のサイモン・クズネッツが創案した経済指標で次の大戦時の戦費に備えての経済指標との意図があったのですが、彼は1934年の連邦議会上院への報告で、この経済指標の数値が国民の「豊かさ」や「幸福感」を表す社会厚生指標ではない、との警告を発しています。ヨーロッパでは、戦費は無論のこと、売春や薬物取引までもGDPにカウントされているのです。「骨太の方針2017」の一瀉千里のGDP信仰は、この数年後にその成果や当否はともかくも、デジタル・トランスフォーメーション(DX)のブームが押し寄せることになります。「生産性向上」は、第一に「やりがい」のモチベーション3.0を基盤とするにもかかわらず、デジタル化で何とかなると考えている企業組織の幹部の浅はかさに呆れるばかりです。その幹部自身が部下に任務の「やりがい」をマネジメントできていないガバナンス不全であることに気付いてもいないのなら、どれだけ優れたアプリケーション・ソフトでもってしても生産性は上がるはずもありません。今を生きる人々のニーズ、すなわちマーケットの求めるものは、時代環境の激変に伴って大きく変化しています。それは、市場が単に受給の経済的均衡を決定要因としていた時代から、成熟社会にあっては社会心理的な価値概念を加味した価値観の均衡へと変位していると私は考えています。したがって、昨今の「顧客満足度」から「顧客幸福度」への指標への移行は、時代的必然であると受け止めています。歴史的名著である『経済発展の理論』でイノベーションを定義したシュンペーターは、イノベーションを5つの類型に分類しており、その三つ目に「マーケット・イノベーション」、すなわち新しい市場の開拓を挙げています。ポジティブ心理学の知見で吟味すれば、「今日を生きる人々」は、「感情的で瞬間しか続かない、スパンの短い満足感であるHappiness」ではなく、「身体的、精神的、社会的に良好で満たされた持続的な状態であるWell-being」を求めていると、私は解析するのです。
私が問題視する「マーケットイン」について少し触れておきます。1950年代に米国で起こった劇場に関する歴史的出来事を想い起こして欲しい。大戦後映画産業のハリウッドの最盛期が急速に進み、地域の劇場は次々に映画館に変わっていきます。地域で観ることが出来るのは、ブロードウェイ製作の舞台のトライアウトに(舞台をバラシアップするための試演)と位置づけられた地方巡業公演のみになってしまう。そのことに危機感を持った若い演劇人とニューヨーク大学の演劇科の学生たちを中心に、「マーケットイン」による演劇の価値観のブロードウェイ一極化を懼れた「リージョナルシアター運動」が起きて、それをフォード財団が財政的にバックアップした歴史的出来事を、です。1950年にはワシントンD.C.にアリーナステージが、その3年後には現代演劇協会の招聘で『欲望という名の電車』や『埋められた子供』を来日上演しているミルウォーキー・レパートリーシアターが誕生して、現在ではNPO法人格の地域劇場は全米各地に50を超えると言われています。諏訪東京理科大学共通教育センター准教授、ニューヨーク市立大学大学院, マーティン・E・シーガル・シアター・センター客員研究員を歴任した旧知の青野智子氏は、世田谷パブリックシアターのアーツマネジメント講座で、米国のリージョナルシアターが地域住民に「自分たちの劇場」という意識を醸成して市場の論理に飲み込まれて公益性不問の危機にある劇場の「公共性の賦活」させたとの主旨の 「アメリカ・リージョナルシアターにおける公共性の発見」という論文を書き記しています。この米国における「リージョナルシアター運動」の歴史的意義から何も学んでいない当時の文化政策部会委員たちの無定見さと無分別さには呆れるばかりです。そして私はコンセッション方式による「公益性と公共概念の失速」から、拙速に過ぎた制度設計による「指定管理者制度」の落着点を想起せざるを得ないのです。「稼ぐ文化」による文化芸術の外部環境の変化が遂に「公益性と公共性の失速」にまで至ってしまうのではないかと危惧するのです。しかも、人間的な共感をベースとした公共文化施設と、完全機械化によってもサービスの質が不変な駐車場を同梱してしまう乱暴な制度設計は禍根を残すとの危惧は当時からありましたが、愛知芸術文化センターのコンセッション方式の採用で「公共と公益の失速」というかたちで現実となりました。
「Public」は、ラテン語の「populus(人々)」と「-icus(〜の)」が組み合わさった「publicus」が語源で、これが「人々のもの」という意味になり、現在の「Public」へと発展しているのです。したがって、公共文化施設は「一部の愛好者」のために設置されているのではなく、第一次基本方針(2002年閣議決定)にあるように「(2)共に生きる社会の基盤の形成 文化は、他者に共感する心を通じて、人と人とを結び付け、相互に理解し、尊重し合う土壌を提供するものであり、人間が協働し、共生する社会の基盤となるものである」、「文化芸術は、芸術家や文化芸術団体、また、一部の愛好者だけのものではなく、すべての国民が真にゆとりと潤いの実感できる心豊かな生活を実現していく上で不可欠なものであり、この意味において、文化芸術は国民全体の社会的財産であると言える」となるのです。 そもそも、大平総理の施政方針演説にあった「物の豊かさから心の豊かさへ」を曖昧で薄い言辞を設置根拠としたホール建設ラッシュには、当初からボタンの掛け違いがあったと総括しなければならないと、私は考えています。私はホール建設ラッシュのあった頃から「演劇愛好者が沢山いるまちなんか気持ち悪い」と言い続けていました。当時は演劇評論家を生業としていましたから、焦点はどうしても演劇に偏していますが、買取の鑑賞事業の関連事業として「演劇体験教室」のような催事を設けるのが、当時の観客開発のスタンダードでした。これが、上演される鑑賞事業の舞台を深く理解するための事前ワークショップとして、「人間はその行為と実践において、本質的に物語(ナラティブ)を語る動物」と人間を定義したアラスディア・マッキンタイアの知見等をバックボーンとするメソッドに裏打ちされたプログラムなら納得できたのですが、ただの「演技の体験」でしかなく、それに何の意味があるのかはなはだ疑問を感じるものでした。人間は「想像力と創造力」を働かせ「物語(ナラティブ)」を紡いで、そのことによって様々な事象や他者理解をしている、との糸口を提供する目的のワークショップならいざ知らず、「演技を体験」するためだけに数時間と数日のワークショップを開催して何が変わるのか、と私は冷ややかにそのスタンダードを見ていました。その土地の気候や風土や慣習等の衣食住に関わる日常生活に深く根を張っている習い性は頑迷で変化させることは困難がつきまといますが、それだけにいったん動き始めると雪崩を打つように変化し始める成人病予防の減塩食推進キャンペーンのようなソーシャル・マーケティングには成果の顕著に出ることが稀にあるのですが、趣味嗜好に属する演劇やクラシックの愛好者を育成しようとする試みや育成は、私はほとんど不可能に近いと考えています。習慣や慣習に変化をもたらすソーシャル・マーケティングの重要な使命である「集団的同調」は決して起きないと断言できます。
私が「カキの森」に喩えているのは、拙著『芸術文化行政と地域社会』から引用すれば、「雨が森に降り、森林の蓄えていた栄養分が伏流水に溶け込んで川となり、流域をうるおし、海に流れ込んで海藻や植物プランクトンの生長を促し、豊かな魚介類を育てる」という社会的機能であり、敬愛する宇沢尚文先生の提唱した「社会的共通資本」の制度資本としての文化芸術であり、2010年代初めに一般財団法人地域創造が「公立の文化拠点は文化的コモンズ(共同利用地)の形成を」と提言していた社会の共有財産(Public Domain)としての劇場音楽堂のメタファーです。社会包摂型劇場経営とは、国民市民の「生活の質の向上」をミッションのひとつと考える、「みんなの広場」(劇場法前文)としての劇場音楽堂の社会的存在価値を言っているのです。そして、その劇場音楽堂の定義の実装化が、可児市文化創造センターalaの2008年から2012年の4年間集計でチケットの販売数を3.68倍、パッケージチケットのセット販売数を8.75倍、来館者数を23万人から47万人に引き上げるというエビデンスをアウトカムしたのです。劇場音楽堂の本質的な価値とは、文化芸術の芸術的価値と社会的価値が織り成す時空によって、近年よく使われている言葉であらわせば国民市民にとって安心できるWell-beingのプラットフォーム、すなわち個々人の価値観を超えて多様で普遍的で利他的なつながりを生み出す社会的装置であることで、経済的利益の適正化をアウトプットすべきと私は思い続けています。
ノーベル経済学賞の「アギヨン=ホーウィット理論」で社会のいまを俯瞰する。
ここまで書き進めてきて、今年のノーベル経済学賞が、「イノベーションと経済成長との関係」についての理論的研究で名高いフランスのフィリップ・アギオンと米国・ブラウン大のピーター・ホーウィットに贈られて、それはともにシュンペーターの「イノベーションと経済成長の定義」を数式化ことにあるとのことで、数理経済学は端から私には無理なので、その概要と解説だけでも読みたいと資料を検索してみました。ちなみにその数式は以下の通りです。
成長率 g=λ×lnf()(1+γ)g=λ×\ln(1+γ)g=λ×ln(1+γ)
ここで、λ(革新頻度)は新しい技術・企業がどれだけ生まれるか、γ(改良幅)はその革新がどれほど生産性を押し上げるかを意味する。
とあるのですが、高校3年時に数学Ⅲと世界史が選択科目となっていて迷わず世界史を受けることにした私のような者には、上記の数式が何を意味するのか皆目見当がつかないのですが、日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授によれば、2025年のノーベル経済学賞は、経済成長を「創造と破壊の連鎖(creative destruction)」として捉え直した3人の経済学者――フィリップ・アギヨン(仏)、ピーター・ホーウィット(カナダ)、ジョエル・モキイア(蘭)に授与されたのであり、これはシュンペーターの「資本主義の本質は創造的破壊にある」と喝破し、資本主義とは絶対的な安定を意味するのではなく、絶えざる変化の連続と急速な転換による不安定な連鎖を本質とするシステムだという非近視眼的知見、資本主義の宿痾の数式化を顕彰したものと言えるようです。その「創造と破壊の連鎖」こそが経済成長の発火点となるとの「アギヨン=ホーウィット理論」が高く評価されたという解説でした。たとえば、「色鮮やかな思い出」を売っていると自社を事業定義してカラーフィルムの世界的トップランナーだったイーストマン・コダック社が、デジタルカメラの急速な普及と進化を見誤ってしまって、大成功した写真フィルムの業績に悪影響を与えるとの理由から既に開発していたデジタルカメラの商業化を見送るなどしたため技術革新の波に乗り遅れ、2000年代以降のフィルム市場の急激な衰退にともない、2012年に企業倒産した事例は、米国の実業家で経営コンサルタント、ハーバート・ビジネススクールの教授も務めたクレイトン・クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』でも指摘している、従来製品の改良を進める「持続的イノベーション」と、従来製品の価値を破壊して全く新しい価値を生み出す「破壊的イノベーション」を説明するのに、とてもわかりやすく、以前は講演等で度々使っているので耳タコの向きも多いとは思います。
アーラの館長に就任して掲げた「社会包摂型劇場経営」は、クリステンセンの分類に倣えば、まさしく「破壊的イノベーション」です。別の側面から見れば、生産者主権の「数量信仰・価格主導の趣味・嗜好志向のマーケティング」から、消費者顧客主権の「価値主導の主義・主張・価値観・QOL(生命の質・生活の質・人生の質)のマーケティング」へと、近年迷走しているマーケティングの定義そのものをまったく別のフェイズに移行転移させることになります。それが2010年にコトラーの提唱したマーケティング3.0の価値主導の「マーケティングはより良い世界をつくる」(Marketing is world better)に重なるのか否かは、さらに深掘りして多角的に検証しなければならないと考えています。したがって、「マーケット」も新著『人間の安全保障としての文化芸術』に書いているように「経済的価値の相互交換」にとどまらず、社会の複雑化にともなって「社会心理的価値の相互交換」をも包括する概念となっていると、私は確信的に考えています。今年のノーベル経済学賞を俯瞰的に解説してくださった田中道昭教授は、「アギヨン=ホーウィット理論」を「成長とは、創造(innovation)が破壊(淘汰)を生み、淘汰がまた次の創造を呼ぶ『動的均衡』である」とあざやかなさばきで解説してくれています。「動的均衡」とは、生物学者の福岡伸一氏の生命体が「生きている」といえる状態を説明する際にかならず使う確言で、生物は絶えず創造と破壊を繰り返していながらミクロ的に見ると常に変化しているものの、マクロとしては変化していしないという定常状態という最適化を言い表しています。すなわち、成長とは、創造(innovation)が破壊(淘汰)を生み、淘汰がまた次の創造を呼ぶ「動的均衡」であるということです。破壊と生成との動的な平衡状態が経済成長であり、進化であるとの解が上記した数式ということです。田中道昭教授の説得力は次のフレイズに凝縮されています。「『アギヨン=ホーウィット理論』は、単なる経済モデルではない。『進化を恐れず、痛みを設計する社会哲学』である。創造がなければ活力が失われ、破壊がなければ創造は生まれない。成長はこの二つの緊張の中からしか立ち上がらない。創造的破壊とは、壊すことではなく、再び生き直す力である」。そして、創造(Innovation)/破壊(Destruction)/成長(Growth)/制度(Institution)、この循環が滞りなく回る社会こそが、変化を恐れず、変化を幸福へ変えられる社会である。いま日本に欠けているのは、まさにこの循環の推進力だ。
この「動的均衡」は、生物学的には生命体の人為の加わらない自然の営みとして進行しますが、この概念が経済学、経営学、社会学、政治学、行政学等にも演繹され「成長とは偶然ではなく、設計できる」という革命的なメッセージとしても広く活用されるようになると、経営者や制度設計に携わる行政関係者の思考がどのように働くのかが創造的破壊を作動させて「動態均衡」を現出させるための重要なファクターになります。全国イノベーション調査2020年調査統計報告 (文部科学省 科学技術・学術政策研究所)によれば、従業者数10人以上の企業442,978社を対象母集団として30,088社を標本抽出し、うち12,534社から有効回答を得ています。その統計調査を俯瞰すると、コロナ禍というイノベーションに取り組まなければならない環境下にあったために大企業でも何らかの取り組みは実施されているものの、破壊的創造と認知できる新製品や斬新なサービスを開発し、プロダクト定義やマーケティング等のビジネス・イノベーションに着手しているか終えているとの回答はスタートアップを含めた中小規模の企業が圧倒的に多いのが目立っています。それは当然の結果です。多くの経営者がイノベーションは苦手だと答えています。今まで作り上げたものを能動的に壊して新しいものを作ることは、日本の組織にはかなりのチャレンジです。1987年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・ソローの提唱した経済成長理論を念頭に置き、イノベーションこそが経済成長の唯一の源泉だと考えられていて、ソロー以前の経済学では、資本蓄積が経済成長の源泉とのバイアスや常識の呪縛から自由になった発想、すなわち「破壊的イノベーション」は生まれ難いからです。当然の結果ですが、大企業の経営者は、過去からの連続的成長を促す「インプルーブメント(改善)」を心掛けて、それまでの実績に対して保守的な「持続的イノベーション」に傾斜するのです。「社会包摂型劇場経営」をアーラの中長期的経営戦略として掲げられたのも、それまでの4年間の事業報告書と収支決算書を読み込んで、失うものは何もないと判断したことが大きいと私は思っています。
SWOT分析から中長期的な経営戦略を組み上げる。
劇場音楽堂や芸術団体は、実は何を言っているのか不明瞭な「芸術振興」という言葉にがんじがらめになっていると私は90年代から考えていました。あわせて、頻繁に文化振興に付随して使われる「普及啓発」も対象となる国民市民を上から目線で捉えてエリート意識丸出しで、何を指し示しているのかまったく不明瞭と言わざるを得ません。あるいは、第二期の「文化芸術推進計画(中間報告)として文化庁のウエブサイトにアップされた「マーケットイン」という文化政策用語としては不適切な表現が、文化庁の文化芸術への向き合い姿勢を物語っているのではないかとも考えています。「普及」は「広く一般に行き渡らせること」の意を持っており、「啓発」には「人が気づいていないことを教え示して、より高い認識や理解に導くこと」の意を持つ言葉で上位者から教え諭して「態度や行動を変容させる」という、共感と共創によって価値を共有するマーケティング思考からは大きく外れた語彙です。しかも、2002年に発出された第一次文化芸術の振興に関する基本的な方針には、前掲したように「文化芸術は、芸術家や文化芸術団体、また、一部の愛好者だけのものではなく、すべての国民が真にゆとりと潤いの実感できる心豊かな生活を実現していく上で不可欠なものであり、この意味において、文化芸術は国民全体の社会的財産である」とあり、「国民全体の社会的財産」と目指すべ具体的な使命と任務を明示していて、「普及啓発」とは大きな隔たりがあるとは感じないだろうか。有体に言えば、文化政策関連の文書の一貫性のなさと軸のブレ具合には呆然とさせられます。文化芸術が内包する公共性と、国民市民にとっての「健全な生活を保障する社会共通資本固有の役割」という前提条件を共有して論議を始める時期ではないか、と思うのは私だけだろうか。
そのためには、まず着手しなければならないのは、文化芸術に関わる私たちの「社会意識のイノベーション」ではないだろうか。しかも、従来の意識と地続きである「持続的イノベーション」ではなく、まったく新しい価値を生み出す「破壊的イノベーション」でなければならないと私は確信しています。芸文振の各分野の審査責任を所掌する研究者有識者、アーツカウンシル各分野PD・PO13名によって、2021年に当時の部長指示で特別部会が組成されて、「アーツカウンシルの機能強化」をテーマとして、国民、市民の期待にどのように応えるかを月2回という過密な協議を4か月にわたって「第三次基本方針」閣議決定の前年の2010年に、従来からの「赤字補填」スキームの支援が大きく見直され、リハーサルまでの準備期間の経費を支援して、公演での収入を自主財源とする芸術団体のインセンティブの働く仕組みに変更されます。すなわち「保護政策的文化支援」から「社会的必要性に基づく戦略的投資」への準備がなされます。単一的な「文化振興」から多様な社会的価値の成立を戦術的使命として、文化芸術の機能を活用したビジョンへのアップロードの道を拓いたことは文化政策上、大変重要なイノベーションでした。2017年の第16期文化審議会総会では、当時の井上文部科学戦略官が「今までの純粋な文化芸術の振興にとどまらず,様々な関連分野も含めるということ」を前提にして、当時の井上戦略官の「この価値というのは,公共的価値でございますとか、社会的な価値、経済的な価値、ただ単に経済的な価値というわけではない」との答弁にあるように「公共的価値」を指すとの方向性を持って議論を積み上げました。その会議に立ち会って内容を吟味して、内容とその空気にぢかに触れた部長から私に出された芸文振職員、国立劇場職員対象のリモートによる講演のタイトルが「社会の中の文化芸術」だったことは誠に印象深い。つい最近、学生劇団自由舞台時代の朋友の故林雄一郎の遺産基金を原資として早稲田小劇場どらま館を活性化して、とりわけ正門通り商店街及び早稲田近辺の福祉施設等への演劇の社会的機能を活用した社会的孤立孤独へのリスクヘッジにしてパーパス経営に転換させようと、私と妻の柴田英杞が早稲田大学文化推進部参与に任命され、その準備をしているのですが、先日柴田による林雄一郎基金のミッションを定立させる目的でロジックモデル研修が行われたのですが、彼女の感想によれば、ここでも「社会的価値」への言及はほとんどなかったということでした。ただ、なかには5年後の中ミッションに「支える・支えられるの、どちらにもなれる場が増える」との記述があり、先行きに期待しても良いのではと思わせるものもありました。ただ、演劇や劇場が何処にもないとの受講者から出ていたことも確かとのことでした。「社会包摂型劇場経営」を2008年に掲げてから20年近く経って、包摂型プログラムを計画実施する公立文化施設は多くなっていますが、大切なのは「手段と目的を混同しない」ことと私は思っています。
アギヨン=ホーウィット理論の社会実装であり、創造的破壊を「幸福の構造」に変える鍵であり、その新たな創造や再構築のためは、まず自分を壊す(呪縛されている常識やバイアスから遁れる)ことが非常に大切なのです。その最適解を導く際のツールとフレームワークとしては、「SWOT分析」、「PDCAサイクル分析」、「ロジックモデルツリー分析」が一般的には有効とされています。私の現場での実践知から言えば、「PDCAサイクル分析」、「ロジックモデルツリー分析」はプロジェクトの計画段階と改善段階で非常に有効であり、公共文化施設や芸術団体の中長期的経営戦略策定には「SWOT分析」が最適解の輪郭を描いてくれます。私は可児市文化創造センターの館長に就任した年にウエブに2ヶ月間で書き下ろした『集客から創客へ-回復の時代のアーツマーケティング』(https://kpac.or.jp/essay/#arts-marketing)にその詳細は書きとめてありますので参照していただきたい。下記にSWOT分析を図解だけを転載しておきます。私のアーラのSWOT分析の詳細もウエブ上の本文内に書き記してありますので、参考にしてください。可児市の公共劇場に新しい価値を付加するための「破壊的イノベーション」の起点がそこにあります。本来は全職員でのブレーンストーミングや合議で行うのが理想なのですが、就任直後には、その職場環境にはなかったこともあり、大学との兼務で非常勤の身分で館長就任する前年に開館後4年間の事業分析、財務資料分析、赴任する前年に実施された「政策評価のための基礎調査」の分析をしたのちにSWOT分析を私一人でやって可児市文化創造センターalaを新しいフェイズに移行させようと考えていました。

内部環境と外部環境を総合的に洗い出して、機会と脅威、強みと弱みを書き出します。そのうえで、その記したマトリックスを一つひとつ検討していきます。たとえば弱みとして近隣の大都市である名古屋市からも名鉄で小一時間かかる地政学的な「弱み」は、一般的には評価機能の東京一極集中により、東京での評価が「全国区」であるのに対して関西地区、中京地区で上演される舞台と劇場ホールの評価は「関西ローカル」、「東海ローカル」でしかなく、如何ともし難い固定化されたWeakness(弱み)として挙げているのですが、あわせて「外部からの刺激のなさ(内部で自己完結してしまう職場環境=地域文化施設に共通する課題)を挙げています。その一方では、人口10万程度の地域にとって、Opportunity(機会)として地域文化施設を対象とする補助制度が「舞台芸術の魅力発見事業等の地域文化振興補助制度の進捗」を挙げているように地域文化に関する外部環境は拡張の方向に大きく動き始めていました。就任時には可児を「かに」とは呼んでもらえない地政学的な弱みが、逆に反転すると劇場ホールの成果が都市圏とは異なりブローアップされて認知が一挙に進む「強み」でもあると多角的に俯瞰すると逆転の発想となるという分析をしていました。この分析検討のプロセスで想起された可児市における劇場の在り方である「人間の家」が、アーラの地域拠点契約、アーラコレクション・シリーズ、まち元気プロジェクトによる社会包摂型劇場経営の発想の原点となったと言った方が正確かも知れません。
新しい価値を共創共有するプラットフォームとしての地域の公共劇場を。
いま一度想い起こしていただきたい。シュンペーターが提唱したイノベーションの概念である「新結合」(new combination)とは、「従来の常識では組み合わせたことのない要素を組み合わせることによって、新たな価値を創造すること」と定義すべきで、いわば「思い込み」や「常識」から離脱して、思いもよらぬものを結合させて「新しい価値を創造する」ことがイノベーションなのです。それによって「破壊的イノベーション」を作動させて、制度や意識のコペルニクス的転換を企図することで、文化芸術の再創造された価値を共創共有する社会的プラットフォームを創造することがフィリップ・コトラーの提唱するマーケティング3.0の、文化芸術分野での実装化なのではないだろうか。「WYPの賑わい」は、演劇とミュージカルの愛好者によるものではなく、WYPのリーズ市における劇場の存在価値の転換によるものだと理解すべきなのです。それは、同時に生き生きと顧客対応するWYPの職員たちのWYPで働いている誇りを感じ取りました。2000年に劇場コンサルタントや公共劇場関係者でツアーを組んで催行責任者として英国内の劇場を巡ったことがあります。エジンバラのトラバース・シアター、同じスコットランドのスターリングにある大学構内に設けられている子どもたちの理事会のあるマクロバーツ・アーツセンター、150人が在籍するユースシアターを抱えるセントアドリュー市のバイアシアターを回って最後に英国内で高く評価されているWYPの毎週水曜日に開催される高齢者プロクラムのヘイデイズに3日間を費やす日程でした。そのWYPでは、到着した初日にバックステージツアーをしてもらって体育館4棟ほどの広さのある大道具製作をするワークショップや衣装製作室のワードローブ、むろんクォーリーシアター(大劇場)とコートヤードシアター(中劇場)と劇場内の隅々まで案内してもらったのですが、その案内役は劇場に雇用されているグラフィックデザイナーということで少々驚きました。いくつかの質問をしたのですが、給料はデザインプロダクションよりも10%強は低いという。ならば、どうしてWYPで働いているのかと訊いたら、「ここはリーズ市民にとって大切な場所ですから」と表情を変えずに何気なく言葉を継いでくれました。プレイハウスのウエブサイトには「私たちのコミットメント」が掲載されていて「プレイハウスには、平等、多様性、アクセス、インクルージョン(社会包摂)が DNA に組み込まれています。私たちは、プレイハウスを誰もが働き、訪れるための歓迎的で安全で敬意を持った場所にすることに尽力しています」とあって、職員がそのことに高い誇りを持っていることが窺がえます。
顧客体験(CX)を重視する企業が増える中、新自由主義経済思想が社会を覆った90年代で急速に失速してしまった従業員体験(EX)との関係性が現在改めて注目されています。CXとEXは切り離されたものではなく、相互に影響し合う「体験価値」の両輪であり、欧米に比べて生産性の低さが社会課題となっていますが、これを解決に向かわせる処方がDX(デジタル・トランスフォーメーション)のように日本では思い込まれていますが、そのために手を付けるべき初手は、上記の自分事の「やりがい」を経験値として体得する、ダニエル・ピンクの提唱する「モチベーション3.0」を裏付ける言説.なのです。ダニエル・ピンクはゴア副大統領のスピーチライターを経て、社会評論やビジネス関連の論文をニューヨークタイムス、ワシントンポスト等に執筆している文筆家で、生存本能に基づく生き延びるための「モチベーション1.0」、外発的動機付けである信賞必罰に基づくアメとムチの「モチベーション2.0」も有効に機能しなくなった現代にあっては、「やりがい・生きがい」という内発的動機によって組織を強化し、健全で活気ある社会を形成して、新しい価値を共創共有する「モチベーション3.0」こそが求められていると著書『モチベーション3.0』で提起しています。つまり、企業組織の成長や経済成長とは、単に生産性の上昇ではなく、変化を受け入れながら幸福を守る、あるいは社会価値を創造するシステムの再構築であることに気付くべきなのです。この「気付き」の全市的な集積の結果が、「マーケティング3.0の実装化」によるWYPの「にぎわい」だったのではといまでは思っています。
ジャン・ジオノから教えられた私たちの仕事の意味。
宮城大学・大学院の最後のゼミ生たち10数人が、一人一冊の絵本を携えて着任したばかりの可児市文化創造センターalaを訪ねて来ました。2008年の3月でした。その絵本の中にジャン・ジオノの『木を植えた男』があって、心を大きく揺さぶられました。私がこれから可児市でやろうとしている私の仕事はこれなのではないか、と劇場経営によって健全なまちづくりに寄与したいと考えていたものの、先行きにいささか不安を感じていた気持ちは激しく揺さぶられて、その昂ぶりがしばらくはおさまりませんでした。『木を植えた男』は、フランスのプロヴァンス地方の荒れ果てた高地をあてもなく旅していた若い「私」は、この荒野で一人暮らしをしている寡黙な初老の男ブフィエに出会います。ブフィエは一人息子と妻を亡くしたこと、特別にすることもないのでこの荒れた土地を蘇らせようと思い立ったことなどを「私」に話します。第一次世界大戦が始まり、従軍した「私」は彼のことを思い出すこともなかったのだが、5年後に戦争が終わり、わずかな復員手当てを貰った「私」は、澄んだ空気を吸いたいという思いから、ふたたびプロヴァンスを訪れます。かつての荒野に近づいた「私」は、荒野が何かに覆われているのに気付きます。近付くと、それが背丈ほどに成長したナラの木々だと分かります。第二次世界大戦など様々な危機があったけれども、「私」の友人である政府役人の理解と協力などもあって、一年がかりで植えたカエデが全滅したりしたことはあったが、森は大きな打撃を受けることはなかった。ブフィエはそんな出来事も気にせず苗木を植え続け、いつしか森は広大な面積に成長していた。森は広大な面積に成長していた。森が再生したことで、かつての廃墟にも水が戻り、森の中には小川のせせらぎの音が聞こえ、鳥のさえずりが心を和ませ、新たな若い入植者も現れて、楽しく生活している。子どもたちや若者たちの笑い声が森に響くようになっていたのですが、しかし彼らはブフィエの存在も、ひとりの男が森を再生したことも知らないというのがその物語です。かつて「森と魚貝の連鎖」から劇場はカキの森でなければならないと考えた私にとって、「ブフィエ」の木を植え続けた長い歳月こそ、私たちの仕事だと心が震えました。私は7年間教師として60名近いゼミ生に、学部3年次・4年次週2コマずつ、大学院1年次・2年次に2コマずつ、計週8コマの「文化事業ゼミ」で向かい合ってきましたが、私のこれから携わる仕事が一朝一夕で終えるものではなく、気の遠くなるような長い時間を要することを知っていたのはゼミ生だったことを、ジャン・ジオノ『木を植えた男』で知らされたのでした。そのことにも心が激しく揺さぶられました。私たちの仕事は、ブフィエの木を植え続けた数10年のように誰にも記憶されないかも知れませんが、誰もが等しくその恩恵を受けるという意味では長く生き残る「いのち」であってほしいと願うばかりです。「小さな気付き」が幾重にも積み重なって社会の価値観が変化を始めるのです。「タイパ」「コスパ」を重視するZ世代には響かないでしょうが、社会の価値観に変化を与えるということは、誰にも顧みられなくとも、それほどの大仕事なのです。
次回は、このマーケット・イノベーションの提案を、セオドア・レビットの『マーケティング近視眼』と『無形性のマーケティング』を通して吟味してみたいと考えています。