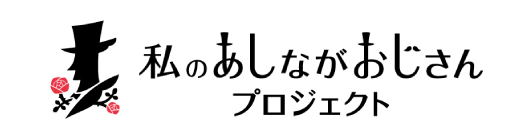Essay
エッセイ・連載
第29回 私たちはいま何処にいて、何処に向かっているのか-「公共の概念」が失速する時代と向き合って。
2021- 「人間の家」の劇場経営をナビゲートする。
2026 年 01 月 30 日 (金)
劇場経営・文化政策・アーツマーケティング アナリスト 早稲田大学文化推進部参与 衛 紀生
ドラッカーを再読して、劇場経営の来し方を検証してみる。
館長辞任後に、それまでの軌跡を書き留めて次の世代に少しでも承継しておきたいと約2年弱の時間を費やして書き下ろした『人間の安全保障としての芸術文化―人間の家・そのアーツマーケティング』も、脱稿してみれば書き漏らしていることが多々あって、その後の勉強で信じるに足りる知見を得て、補綴する意図でウェブサイトでの本連載を借りて思い積むことを絞り出すように書いています。上梓するまで2年半のかかった著作のモチベーションを深掘りしてみると、著作内に書ききれなかったことが山積していることにも気付きました。たとえば、私が社会科学における「予言の書」と思い続けている93年刊のP・F・ドラッカーの『ポスト資本主義社会』がその代表格と思っています。前回の文末に「マーケット・イノベーションの提案を、セオドア・レビットの『マーケティング近視眼』と『無形性のマーケティング』を通して吟味する」と記して次回への連続性をコミットしたのですが、その前に新著の通奏低音に間違いなく「ドラッカー」が流れていることに前回を脱稿してからの短い時間で気付かされました。
私は大学で演劇を志向していた頃から、70年代も80年代を通して「経営」についてはほとんど無関心でした。「経営」について最初に関心を持ったのは、当時7紙の新聞を購読していて、そのうちの日経新聞に掲載されていた「やさしい経済学」で、当時慶應義塾大学総合政策学部教授で同学部長を務めていらした井関利明氏の「リレーションシップ・マーケティング」の概念に出会って、それが「顧客創造」に強い影響力を持っていると感じたのが嚆矢だったと記憶に刻まれています。93年のことです。その前年に私は劇団離風霊船の長野県・岡谷市での市民参加事業のための合宿を通して出来た人間関係と、そこでの劇団員と市民とのあいだでの経験共有によるリレーションシップの強さから派生した「創客」の誘客効果の萌芽を目撃していました。あわせて、93年には私のロジックに強烈なインパクトを与えることになる長崎の障害児たちの「のこのこ劇団」との出会いと交流を通して、文化芸術の社会的価値の存在をはじめて意識して、当時は週に3館で杮落し公演が行われるほどの「ホール建設ラッシュ」へのハコモノ批判と税金の無駄遣いバッシングが、「受益と負担の圧倒的アンバランス」から生じている認識の齟齬によるものと確信して94年に岡山県立美術館でのシンポジウムで「創客」の提案を発したのです。井関先生とのご縁で「マーケティング」に強い関心を持ったことが「経営」に足を踏み込む契機になったことは、その後にドラッカーの『マネジメント』を読むことになって「マーケティングは事業体の第一の機能」であり、「イノベーションが第二の機能」との記述から後付けで認識することになります。
そもそも私の読書遍歴は天邪鬼と言えるもので、学生劇団に在籍していた頃に戯曲解釈に言語論を援用すれば印象的な読み解きより深掘りできるのではないかと、一年生の秋に同世代の一部に動きがありました。その折に、すべての同期生が選んだのは吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』でした。私は当時の大学近くの戸塚の古書店のなかで良心的な品揃いで高く評価していた文献堂書店で目をつけていた、在野研究者であった三浦つとむ氏の『認識と言語の理論』を寒い懐具合から思い切って購入しました。この『認識と言語の理論』は、およそ半世紀後にノートルダム大学の倫理学教授アラスディア・マッキンタイアの提起した「ナラティブ」を解釈するうえで大いに役立つことになりました。ことほど左様に、天邪鬼であるので、最初に触れたドラッカーの著作は、舞台芸術環境フォーラムを立ち上げた直後に現在は妻となっている柴田英杞から贈られた『非営利組織の経営』でした。芸術経営や劇場経営にはまったく興味を持っていなかったので、当時の私にとってドラッカーは圏外だったことを告白しなければなりせん。ところが、『非営利組織の経営』の序論で私の心は彼の記述にわしづかみにされました。「非営利機関は、人間変革機関である。その『製品』は、治癒した患者、学ぶ子供、自尊心をもった成人となる若い男女、 すなわち変革された人間の人生でそのものである」に私の気持ちはがっしりと掴まれてしまいました。
さらに、ドラッカーは、非営利組織に重要な要素として「マーケティング」を挙げていることには心底から驚かされました。マーケティングをしないで非営利組織を運営すると、自分たちの独善的な考え顧客に押し付けることになって「顧客離れ」と「支持者の離反」を生じさせてしまう、と記述の穂を継いでいます。前述したように井関利明先生に私淑してリレーションシップ・マーケティングこそが「マーケティングの本質」だと心得ているので、「善きことをマネジメント」するためには結ばれている関係を棄損することなく、より強い信頼感によって補強し続けて長期的な関係づくりを志向しなければならないと考えました。非営利組織とは、NPO、NGO、医療機関、教育機関、介護を含めた福祉機関、自然保護団体、芸術文化団体等を指しています。米国のNPO、英国のチャリティ法人格、日本では公立の劇場ホールを所掌する自治体出捐の財団法人もその範疇に含まれます。『非営利組織の経営』でドラッカーからの強かなインパクトを受けて、衆知のようにバブルとその崩壊という資本主義の揺らぎの予兆を実感していた私は、阪神淡路大震災のさなかに『ポスト資本主義社会』を購入して、これからどのような変化が社会を襲ってくるのか、それによって私たちの生活や価値観はいかなる変化を強いられるのかというトラッカーの予言めいた知見を覗いてみたくなったのです。あわせて、およそ20年前に刊行されたドラッカーの古典的名著とされる『マネジメント』を同時進行的に読むことになります。さらに加えて、北海道劇場計画に主査として関与することになり『創造する経営者』にも手を付けて、「未来を予測する最良の方法は、未来を創ることだ」(The best way to predict the future is to create it.)が私たちのように生活者と向き合う人間の任務であり、使命ではないかの示唆をドラッカーから受けることになります。
「顧客の創造」とは顧客を満足させることではない。
『マネジメント』でドラッカーは「企業とは何かを理解するには、企業の目的から考えなければならない」と述べて、繰り返し「顧客の創造」が事業体の究極の目的であることを記しています。「企業の目的は、それぞれの企業の外にある。企業は社会の機関であり、目的は社会にある。したがって、企業の目的として有効な定義は一つしかない。顧客の創造である」と。次に、話の穂を以下のように継いでいます。これは「顧客を満足させる」ということではありません。社会は常に変化していくものであり、それに伴い企業も変化が必要になります。イノベーションを起こし、マーケティングを行い、新たな顧客を創造しなければなりません。この新たな顧客の集合体が新たなマーケット(市場)になります。企業と事業体の目的が顧客の創造であることから、企業には二つの基本的な機能が存在する。すなわち、マーケティングとイノベーションである。この二つの機能こそ企業家的機能である。イノベーションを起こし、マーケティングを行い、新たな顧客を創造しなければなりません。この新たな顧客の集合体が新たなマーケット(市場)になります。ここで重要なのは「顧客を満足させる」ということではありません、社会は常に変化していくものであり、それに伴い企業も変化が必要になる、という指摘です。つまり、先に述べたように事業体の第一の機能は「マーケティング」であり、変化に適応するために第二の機能が「イノベーション」ということです。それによって、事業体の製品・サービスと連動させて外の世界との好循環を戦略的に起こし「顧客の集合体」を形成することとなります。「顧客を創造」して、その「集合体」を形成することが企業及び事業体の社会に果たすべき使命と明示的に断言しています。
しかも、ドラッカーは、AIに依存して何事も解決しようとする時代の到来に警告を発するように、「『イノベーション』に成功する者は、右脳と左脳の両方を使う。数字を調べるとともに、人を見る。機会を捉えるにはいかなるイノベーションが必要か分析を持って知る。しかる後に、外に出て、顧客や利用者を見、彼らの期待、価値、ニーズを知覚によって知る」と書いていて、分析力や論理的思考に優れた左脳のみでは、私たち人間がどうしても捉えられている「常識」や「多様なバイアス」から解き放たれた新たな発想には行き着かないと指摘しています。イノベーションにおけるAIの機能の限界を見通しているようにさえ思えます。例えば、JAXAが月面探索機SORA-Qの開発設計に宇宙工学の専門家ではなく、玩具メーカーのタカラトミーをパートナーに採用したとの最近のニュースが、左脳にとらわれない右脳の自由な働きこそがイノベーションにおける重要な役割を物語っていて非常に興味深い出来事でした。
しかし、ここで「顧客の集合体」をドラッカーは「マーケット」と呼んでいますが、私はこれに異を唱えます。それは『マネジメント』のおよそ四半世紀後に心理学分野で立ち上がったペンシルバニア大学のセグリマンによるポジティブ心理学の知見によって裏付けられます。セグリマン教授は、従来からの心理学は病気を治すための努力はしてきたが、「どうすればもっと幸福になれるか」についてはあまり研究してこなかったことに気付き、心理学は人間の弱みばかりでなく、人間の良いところや生まれついて持っている積極的な心性を研究する学問でもあると指摘しています。さらにドラッカーが『マネジメント』の執筆時とは、顧客はもとより潜在的顧客も一時的な満足感よりも、自身の存在を癒すための自己肯定感とその持続継続性を担保できる「身体的、精神的、社会的に良好で満たされた持続的な状態であるWell-being」を求めていると私は考えています。これが近年、「顧客幸福度」とあわせて「従業員幸福度」が重要な指標として急速に浮上してきた「現実の社会」を如実に物語っていると確信しています。それは、ドラッカーも『ポスト資本主義社会』で看破しているように、物々交換をより取引を軽便にするため発明された「カネ=資本」が目的となり製品やサービスを作り出して物流のネットワークに乗せるより「カネがカネを生む」仕組みの方がコスパもタイパも良いと、さらに証券化によってインターネットで即座に取り引き出来ることから金融資本主義が白昼堂々と跋扈して、格差はより大きくなり、分断が亀裂に進行してさらに助長させているのが「現実の社会」なのではないか。私がアーラの館長に就任した2008年の「リーマンショック」の教訓に立ち帰って、「カネ本位制」の精神をあらためて経営者は足元を再度見詰め直す必要に迫られていると私は思っています。近年、日本の労働生産性の低さを国際比較で盛んに言い募っている風潮があり、その回復手段として猫も杓子もデジタルトランスフォーメーション(DX)に一瀉千里の勢いですが、しかし、新自由主義経済思想が一般化されて以来経営の書から姿を消した「従業員満足度」をいま一度思い起こしてみるべき時ではないかと私は思います。「顧客幸福度」とあわせて表裏の関係である「従業員幸福度」を事業体経営の軸に据えて、その一人一人が「社会の貢献者」として自覚できるようにするのが企業や組織、事業体の正しい経営の在り方であり、まさしくそれこそが「マネジメント」なのではないだろうか。
職員一人ひとりを「社会の貢献者」として。
そのために必要なのは組織全体での「反復学習」だとドラッカーは『ポスト資本主義社会』で念を押すように述べています。少し長くなりますが、『ポスト資本主義社会』からその箇所を引用します。「知識労働者とサービス労働者の生産性の向上には、仕事と組織に継続学習を組み込むことが必要である。知識はその絶えざる変化のゆえに、知識労働者に対し継続学習を要求する。(中略)しかも、生産性向上のための最善の方法は、人に教えさせることである。知識社会において生産性の向上を図るには、組織そのものが学ぶ組織、かつ教える組織とならなければならない。」と、実際の経営を進めるうえで、非常に難しい課題を提示しています。2006年11月に開館して4年半を経ていた可児市文化創造センターalaの館長就任の依頼を受けて、私はいくつかの作業を正職員として具体的に組織をマネジメントするために自分に課しました。ひとつは、どうしてもやらなければならないこととして、4年半の事業別、分野別の収支をエクセルシートに落とし込んでの詳細な分析でした。一見して即座に目立ったのは、担当者の趣味嗜好に偏った事業の組み立てで、文化芸術になじみのない市民にアプローチしなければとの戦術が決定的に欠如している点でした。100億という巨額な設置費を投資しているのですから「戦略」は明々白々なのに、それを具現化するための「戦術」がまったくないという杜撰さがエクセルで分析した数値でも明らかでした。大学教員との兼務期間を終えて正規職員の館長に就くことになる2008年に事務局長として私を支えてくれた篭橋義朗氏(現館長)から見せられた全国の劇場ホールの収支比率一覧によれば、アーラも2006年までは、事業費4000万円以上の括りの中で、総支出6445万8000円、入場料収入2069万円で収支比率32.1%、つまり100円を使って32円を売り上げるという絶望的な経営状態で、その括りの中で全国ワースト6位でした。可児市民と文化芸術の心理的な距離を縮めて親和的な空気を醸成しなければならないのに、前述の事業選択の偏りばかりか、価格政策に何らイノベーティブな工夫が見えない。さらに竣工前からアーラが目標にしていた世田谷パブリックシアターからの買取公演でさえ可児市民を視野に入れていたとは到底思えない舞台を高値で押し付けられているとしか思えない散々な数値でした。当時の世田谷パブリックシアターの地域とのネットワーク計画を大学教員時代に聞かされていた私は、その現状を自分事として目の当たりにして、その計画にWIN-WINの中長期的な戦略が組み込まれていないと思いました。次に手を付けたのが、劇場経営にまったくの素人だった私は、大学の教員だった経験で少なくとも自分の強みだった「ゼミ」を隔週開催して職員の業務として設けることでした。はからずも「仕事と組織に継続学習を組み込む」ことを出発点にできたのです。
さらには、前述の長崎の「のこのこ劇団」との出会いが私に強烈なインパクトをもたらしたのは、私がそれまでの20年間を「常識」や「バイアス」に安住して劇評家を生業にしていたからだとの恥辱にみちた自省があり、何らかの違和感を持った時こそ、その違和感を深掘りするのが自分の知見を研ぎ澄ます機会であり、正しい研究姿勢だと体験的に考えていたので、自分が何かに憑りつかれていないかを確認することが現実の事象と向き合う基本姿勢となりました。「創客経営」も「森と魚貝の連載と公共劇場」も「社会包摂型劇場経営の循環経営」も、その自己点検を経てから導き出した成果だったと今にして思います。さらに、直近で想起されてきている98年のウエストヨークシャー・プレイハウス(WYP)初訪問時に感じた多くの市民による賑わいは、芸術愛好者によるものではなく劇場活動の全体像から発せられる空間の心理的な安全性による「マーケットからプラトフォームへの転位」も、「賑わい=マーケット」という常識に縛られている私自身の誤謬であり、そこでは「マーケティング」自体の定義の転換をも包含しているのではと、最近は思っています。これは、ガルブレイスの依存効果以来の「数量信仰」に憑りつかれてコトラーが『H2H(ヒューマン・トゥ・ヒューマン)人間中心のマーケティング』で、筆鋒鋭く「利益至上主義のマーケッターの行き過ぎた非倫理的行動により、(中略)マーケティングのイメージは近年悪化の一途を辿っている。大半の人は『マーケティング』と聞くと、嘘・欺瞞・・ごまかし・迷惑・操作的といったネガティブな言葉を連想する」と批判しています。
「イノベーションの第一歩は陳腐化したものを計画的に捨てることである」。
表題は、ドラッカーの「イノベーション」への明解な見解です。時代環境の変化から生じる価値観の変容によって陳腐化した生産や流通の制度を練り上げたプランによって廃棄して、新たな価値を生み出すことが「イノベーション」です。それは「変化」に対する処方箋と言えます。私たちを取り巻いている環境は少しずつであっても「変化」しています。したがって、放置すればいかに実績を誇るシステムでも、必ず時間の経過によって陳腐化をまぬがれません。しかし、それが人知を超えて急激に進捗することがあります。私たち人間は、その人知を超えた時間をコロナ禍で経験したと思っています。「VUCAの時代」と言わる見通すことの困難な連続的な変化の時間がそれです。「V」はvolatility(不安定・気まぐれ)、「U」はuncertainty(不確かさ・当てにならないこと)、「C」はcomplexity(課題の絡み合った複雑性)、「A」はambiguity(曖昧さ・意味の多義性)の最初の文字を組み合わせたビジネス新語で、まったく掴みどころのない変化や変動の時代を指しています。こうして改めて「VUCA」を俯瞰してみると、実は何一つ指し示してはいないのではと思い滞ってしまう。
そのようなイノベーティブな発想が困難な時代にあって、マーケティングの巨人と言われているセオドア・レビットが1960年に発表した歴史的論文『マーケティング近視眼』は、その輝きを増しています。無視すると、たちまち衰退期を迎えてしまうほど変化のスビートは速くなっています。自らの事業をどのように定義するかが企業や事業体の未来を創造する決め手となり、事業の衰退期を回避して、リスタートを可能にすることにもなるとの問題提起をレビットはこの論文で提起しています。事業定義を誤ると企業・事業体は衰退期を迎えると説得力のあるロジックを展開しています。レビットが論文内で挙げている事例で有名なものは「ハリウッドの衰退」です。レビットは「ハリウッドの衰退」を、テレビ出現を競合相手と捉えてしまって、自らを「映画産業」と定義したために、マーケットの拡張の機会と考えなかったからと分析しています。現に「テレビの出現」で映画館に足を運ぶ観客が当時は40%減ったというデータがあります。一方、ディズニー社は「エンターメント産業」と自己定義していたためにテレビにも進出して、テーマパークにもマーケットを伸展させ、ニューヨーク42丁目の伝統ある廃劇場ニュー・アムステルダム劇場をリニューアルして『美女と野獣』でブロードウエイにも進出したのです。つまり、マーケットの拡張性を「事業定義」によって獲得したわけです。ハリウッドが自らを「映画産業」と定義するのは至極当然のように思えます。オーケストラや劇団は「舞台芸術産業」と自らの事業を定義できますが、それではベネフィット(効用・利得)の将来に向けた拡張性に欠けていると私は考えます。レビットは「顧客はサービス商品を買うのではない。その商品が提供するベネフィット(効用・利得)を購入しているのだ」と主張していて、顧客は商品サービスそのものを必要としているのではなく、その商品ザビースによってもたらされる「期待価値」或いは「達成可能価値」を得るために購入するのだ、としています。
資本主義も民主主義も振り子のように揺れながらトライ&エラーを繰り返して進化している。
競争優位の経営戦略研究の大家であるマイケル・ポーターと社会貢献コンサルタントのマイク・クラマーによって「ハーバード・ビジネスレビュー」に2006年と2011年に発表された2本の論文『Strategy and Society(競争優位のCSR戦略)』及び『Creating Shared Value(共創価値創造の戦略)』によって提唱された、CSRに積極的・戦略的要素を盛り込んで、従来は「製品サービスの価値」と「社会的価値」はトレードオフとされる「常識」からテイクオフし、経済利益と社会課題の解決を一体的に追求して両者の間に相乗効果を生み出すべきとする歴史的転換と評価できる課題提起と、フィリップ・コトラーが2010年に発表する「顧客を単なる製品やサービスの受け手から価値の共創者(パートナー)と捉える」『Marketing 3.0』(邦訳『コトラーのマーケティング3.0 ソーシャル・メディア時代の新法則』での社会的価値と経済的価値の融合が提唱されたのがほぼ同時期であったことは偶然の一致ではありません。
ミルトン・フリードマンが1970年のニューヨークタイムス・マガジンに投稿した『The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits』(企業の社会的な責任は利益の創出である)で提唱された「企業の第一の目的は所有者(株主)に対する経済的な利益の創出にある」、「格差や環境といった社会的問題は政府に任せ、経営者は株主利益の最大化に専念すれば、結局は富の総量が増えて社会のためになる」とする「株主資本主義」が、富の偏在・独占と格差の拡大によって社会それ自体の機能不全と分断と劣化をもたらして社会を大きく歪ませてしまった、という認識が2019年の米国・ビジネス・ラウンドテーブルの声明の骨子です。株主資本主義への決別とステークホルダー資本主義への回帰と軌道修正のマニフェストと言えます。あるいは、GDPという経済指標の提案者であるサイモン・クズネッツが、「この数値が国民の『豊かさ』や『幸福感』を表す『社会厚生指数』ではない」との警告を1934年の連邦議会上院連邦議会発した警告が85年を経てようやく認知されることになるのです。これらの変化は、カネがカネを生むという「金融資本主義」の登場で喫水線を超えたと言って良いでしょう。さらに「カネ本位=資本主義」の変異株である新自由主義経済のウイルス蔓延で、その副作用である「格差拡大」や「分断助長」によって健全な社会が著しく棄損され、あわせて『ポスト資本主義社会』でドラッカーが予見したように現代社会が抱える様々な問題が、「資本主義の限界」として認識されるようになり、「価値本位主義」がそれにとって代わるようになってきます。その結果、政治の役割と企業活動の境目があいまいとなり、企業活動も製品やサービスで社会課題の解決を担う価値の提供も可能性として大きく存在して、より多くの人々を視野に入れて供給するようになれば、その活動はおのずと公益性を帯びるようになり「公益的価値主義」とでも命名できるフェイズに立ち入るようになります。たとえば、『クリティカル・ビジネス・パラダイムー社会運動とビジネスの交わるところ』の山口周氏の起業家の発想やレベッカ・ヘンダーソンが『資本主義の再構築―公正で持続可能な世界をどう実現するか』で株主価値最大化のみを追求する制度自体が多くの問題を引き起こしているとして、例外として挙げている「従業員所有の世界的企業」の事例である米国・パブリックス・スーパーマーケットチェーンや英国・ジョン・ルイ・パートナーシップやスペインバスク地方のモンドラゴンを列挙していますが、これがただちに現代資本主義の陥穽とも言える「株式会社制度」の歴史的転換を生むとは到底思えません。
私は社会に強烈な衝撃を与える「事件」が価値の変容期となって、長い時間を経て新しい価値の揺籃期となると考えています。その揺籃の時間の中で、私は多様多種なバイアスの塊である「常識」に自分はとらわれていないかとの自問を繰り返します。近年私が承服せざるを得ないと膝を折ったのは、コロナ禍においての世界的知性と言われるジャック・アタリの発言でした。2019年から世界は未曽有の災禍に襲われました。ソーシャルディスタンスや三密が喧伝されて、目には見えないウイルスの恐怖の中で、社会生活を営む上で不可欠なリレーション(つながり)自体が感染に直結しているという脅威にさらされました。人類が誕生して以来、乱脈な支配者の個的欲望から「種を守るための営為」を手放さざるを得ない事態追い込まれた時にジャック・アタリの言い放った「生命維持装置」(Vital Industry)として芸術文化の可能性は、まさしく未曽有の災禍に見舞われて価値の揺籃期に生まれた発言だったと考えています。この変容期が揺籃期でもあるとの社会的循環を私たちは生きています。私的には「連合赤軍事件」の後に来た「しらけ世代」とそのあとの人間を「ネアカとネクラ」に分ける社会の空気、阪神淡路大震災を契機とした「ボランティアとNPO法」、非正規雇用が労働法によって常態化した後の格差社会の常態化と、77年も生きてくると、「変化」の因果関係が明瞭にたどることが可能になります。私は、この繰り返し訪れて社会の価値観や空気に揺るぎをもたらす揺籃の時代を個人的に「The infancy(インファンシィ)」と呼んでいます。前述したように、「顧客満足度」が失速して「顧客幸福度」とその表裏の「従業員幸福度」がクローズアップされる時代の変化も、「格差と分断」による社会の不安定化を回避して、投資行為からの事業体の持続継続性の求められる経済社会からの要請によって大きく変化していると評価できます。フィリップ・コトラーの「マーケティング3.0」も現代では、企業は単に製品やサービスを提供して生活課題を解決するだけではなく、環境問題や教育など「より良い環境づくり」や「社会貢献」といった、社会に良い影響を与え、企業価値を高める取り組みに力を入れることが求められるようになった結果です。また、同時期にマイケル・ポーターと社会貢献コンサルタントのマイク・クラマーによって発表された2本の論文『Strategy and Society(競争優位のCSR戦略)』及び『Creating Shared Value(共創価値創造の戦略)』も、文化芸術サービスの「芸術的価値」と「社会的価値」はトレードオフとされる従来からの「常識」からテイクオフして、経済利益と社会課題の解決を一体的にともに追求し、かつ両者の間に相乗効果を生み出そうとする時代の変化の先駆的研究知見です。成熟した社会では「相互価値交換関係」によって顧客の受取価値と消費行動は決まると考えられていましたが、「マーケット」は欠乏動機に依拠する経済的概念から、「成熟社会」にあっては社会心理的な概念としての変容が顕著となっていると考えるべきではないでしょうか。
「顧客幸福度」と「従業員幸福度」という指標がフォーカスされてきた背景を精査すると、ドラッカーが『ポスト資本主義社会』で看破しているように「公益価値本位主義」がメインストリームとなり、政治活動と経済活動(市場経済)境界が曖昧になるとの指摘があります。市場経済は国民の生活上の不満や不平を汲み上げて課題解決のために製品やサービスを供給して個々人の生活の向上を図る役割を担っています。一方、政治活動における民主主義は、それらの声を汲み上げて、より多くの国民が納得する意思決定をする役割を持っています。しかし、マイケル・ポーターとマイク・クラマーによって発表された2本の論文『Strategy and Society(競争優位のCSR戦略)』及び『Creating Shared Value(共創価値創造の戦略)』は、企業活動は、利潤の最大化のみを究極の目的とするのではなく、生産する製品やサービスで社会課題を解決することをオルタナティブな使命とすることを従来からの枠組みを見直して、本来的な社会での在り方として提起しています。「顧客幸福度と従業員幸福度」への一ページが開けられたと評価できます。さらにドラッカーは、政治が中長期的な課題解決よりも、近視眼的な政策に走ってポヒュリズムに走り、メガステイト化すると予見しています。日本でも「少子化」は70年代から社会課題と考えられていたのに、半世紀後に政策課題として俎上に上がったことは記憶に新しい。そのような社会の在り方を俯瞰すると、ドラッカーの「政治活動と経済活動(市場経済)境界が曖昧になるむとの指摘は達見と言えます。その文脈の中で「公益価値本位主義」での「顧客幸福度」と「従業員幸福度」へのフォーカスがあると評価しても良いのではないでしょうか。
と同時に、私の来し方を振り返ると、私の思考の通奏低音になっているのは、私淑した井関利明先生のマーケティング理論の根幹をなす「リレーションシップ・マーケティング」の生涯価値を重視する考え方と、阪神淡路大震災の際に神戸シアターワークスを組成する時に強い影響を受けたサービス経済学の井原哲夫先生の『愛は経済社会を変える』での主義主張・価値観・社会観・生活信条・生活実感・社会参加と共鳴共感する「つながり」を共創共有する「親密圏形成の課題解決手法」なのではないかとあらためて思っています。91年に『非営利組織の経営』を著わしたドラッカーの深慮を思わずにはいられません。「公益価値本位主義」の有力な担い手として、NPOを挙げているからです。井原先生の卓見に戻せば、先生は、愛という利己心が人を動かし市場とつながりを拡げて「身内意識」を醸成している。経済社会は、愛の性質をたくみに機能させている社会である、との様々な場面でインスパイアを受ける卓見だと私は思います。そして、98年のウエストヨークシャー・プレイハウス(WYP)初訪問時に感じた多くの市民による賑わいは、まさしく「顧客幸福度」と「従業員幸福度」の織りなす劇場の幸せな光景だったのではといまにして思います。「賑わい=マーケット」という常識に縛られている私自身の錯誤があって、「マーケティング」自体の定義の転換をも包含していた光景だったと、最近では確信をもって思っています。さらに、あの賑わいが、愛好者によるマーケットではなく、その空間に生涯価値を感じているWell-beingで充たされたリーズ市民の「プラットフォーム」だったと長い間の疑問が氷解していくのを感じています。井原先生は「人間は身内意識を持てる相手を求めているようだ」と共感と共創による共有価値について記しています。その「身内意識」について、「人間には『自己愛』の範囲を広げるところがある。(中略)『わがこと』のように喜んだり、胸が痛んだりする範囲は自己が広がった部分であり、これを『身内』と呼ぶ」と言葉の穂を継いでいます。『「豊かさ」人間の時代』という.新書版の書籍でも、井原先生は、プロ野球ファンは勝った試合は何回でもニュースで視聴する例を出して、この「身内意識」を説明しています。そして、はしがきに、「愛は人間社会を形づくるうえできわめて重要な役割を演じていることが分かる。しかも、枝葉末節の影響ではなく、社会の骨格に強くかかわっているのだ」と断言してられます。これは、私が宮城大学・大学院の教員時代から深掘りしてきた「マーケティング」に転位の契機をもたらす知見であると考えています。