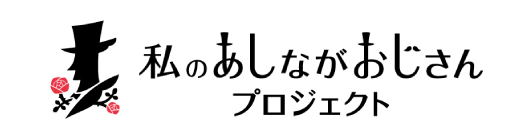Essay
エッセイ・連載
第26回 老いるということ、「認知症」のことが気にかかる年齢になった。
2021- 「人間の家」の劇場経営をナビゲートする。
2025 年 10 月 02 日 (木)
劇場経営・文化政策アナリスト 早稲田大学文化推進部参与 衛 紀生
「還暦」の年に公立大学の教員と兼務で可児市文化創造センターalaの非常勤館長となって、2007年3月に飛び込みで不動産屋に行って広見の田圃の中のマンションに移住して、指定休日を返上してともかくも走り続けました。そして、「喜寿」の年に3年後に館長を退くことを決意しました。2012年5月、館長を務めて6年目に発症した脳梗塞の後遺症で右足と右手先に痺れがあって歩行が困難になったのが直接的な理由でした。自分が勢いを持って仕事をして、その姿と背中を見せて職員を率先垂範で牽引していたので、後遺症の影響を押し隠していてもその姿勢に翳りが生じるだろうし、職員に気付かれる前に辞めなくてはと、前々年あたりから考えていました。館長を辞してからこれまでの道程と経路を書きとめておけば、少しはあとから来る次世代の担い手たちの参考にはなるかな、肯定的にロジックを発展させても、ネガティブに受け止めてアンチテーゼとしての劇場経営を定立させる叩き台になろうと、それは受け手の課題意識に委ねるべきとの考えで構想を立てて、気負いなくメモをしていた備忘記をひっくり返して90年代初めからの演劇評論家時代、早稲田大学講師時代、宮城大学での研究に専念した時代を思い起こして書き始めました。それが近著の『「人間の安全保障」としての芸術文化-人間の家・その創造的アーツマーケティング』として上梓されたわけですが、「喜寿」を数年過ぎていました。
80年代までは毎日毎夜劇場に通って舞台評を書くという舞台の芸術的価値のみに関わり、それ以上でもそれ以下でもなかったのですが、93年に長崎の「のこのこ劇団」との偶然の出会いで発達障害を持っている子供たちの成長に触れて、そのインパクトから「自分はいままで何をしてきたのか」と強い自省感に駆られました。子どもたちが自身の障害を次第にコントロールして社会的排除を克服して行く様子を3ヶ年傍で伴走者として見ていて、「芸術的価値」と「社会的価値」は等価だとの思いが芽生えて、「ハコモノ主義」「税金のムダづかい」との批判に晒されていたホール建設ラッシュは文化振興に資するどころか、国民の文化芸術離れという甚だしい乖離を生んでいるとの危機感を持ってた時でしたので、等価であるべき価値を一体的な経営理念に結実させようと94年に岡山県立美術館でのシンポジウムで「創客経営」を提案することになります。
その翌年の早朝に阪神淡路大震災が起こり、芦屋の教会での救援物資の受け入れと配布のボランティアとして神戸に入り、2週間弱の活動に参加しました。ボランティア・リーダーのガイダンスで彼から目から鱗のコメントを聞きます。「救援物資はあくまでもコミュニケーション・ツールで、ともかく被災者の皆さんに声かけをしてください」です。「目的と手段に明確な一線を画して、チームで共有する」というマネジメントの鉄則で、それ以降の私の戦略思考のベースとなる考え方となりました。それから8か月かけて多くの神戸市民の皆さんと話をして、仮設住宅のコミュニティづくりと子どもたちの心のケアをミッションとする「神戸シアターワークス」を組成しました。演劇の社会的価値を実装化して現場での活動を試行錯誤しながら進めて、その経験を踏まえて、最初の文化政策の書籍である『芸術文化文化行政と地域社会』を97年に上梓します。その中で、漁師が苗木を持って山に登って河川の流域と河川の流れ込む海を豊かにしていく「カキの森の文化政策」と「芸術支援から芸術による社会支援」を打ち出しました。それらをなぞりながら近著を書き進めていたのですが、そうしているうちに私の提案はことごとく即座には理解されないか、無視されてきたことに気付きました。可児市文化創造センターalaの館長になった時に打ち出した「社会包摂型劇場経営」も、当初の4年ほどは「何を言っているのか分からない」が業界人のおおむねの反応でした。業界のオピニオン・リーダー世田谷パブリックシアターの上席管理者から「社会包摂は流行り言葉」と言われて、肩を落として帰ってきた職員もいました。どうも私のいる業界の人間の多くは近視眼的で、現実の時代環境を観察し、空気を察知して先を読むことを視野に入れないで経営をデザインする傾向が強いのではという気持ちは今に至っても払拭できないでいます。潜在する顧客も視野に入れて「関係づくりする共創共有のマーケティング」よりも、数量信仰に囚われている「即効性のある発想である営業志向」に傾斜しがちではないかの懐疑心は拭えないままです。「言葉を揃える」ことが肝要との私なりの現場発想の組織論にしたがって13年間隔週で続けていた館長ゼミの折に職員に言っていた言葉がいくつかありますが、「花よりも、花を咲かせる土になれ」はアーラが市民のために自分たちは何が出来るかを自問する言葉です。
あと1年半で「傘寿」(サンジュ)になります。歩行はリハビリと妻からの踵のもみほぐしで足が上がるようになってストレス軽減の傾向にあります。また、脳梗塞の遠因となった心臓と境界糖尿を治療するために大学病院の内分泌科に退職を決めた年から3年間、年に一度可児から東京に戻って副腎の画像検査を受けて、心臓の心拍数を整える副腎髄質と血糖値を維持する副腎皮質からのホルモンが正常値となるのを専門医に観察してもらいました。その検査は、核医学と言って、微量の核物質を点滴で身体に入れて「コンピュータ断層撮影」(CT)で撮影するもので、当日は乳幼児に近寄らないようにとの注意を受ける代物です。そのために3ヶ年通ったおかげと、脳梗塞発症直後からかかりつけ医から処方されていたニトログリセリンのテープと血液内の糖を腎臓から排出する処方薬のせいで、血圧も血糖値も心電図にも異常は認められないで、ここ数年の年一度の人間ドックでは、すべてのオプション検査を含めて担当医からの意見は「煙草の本数を減らして」くらいになっています。何とか「傘寿」までは「書くことは生きること」の信条を貫けそうだと考えられるようになりました。「還暦」と「古希」は中国の風習に倣った賀寿の祝いですが、それ以外の「喜寿」以降の年祝いの起源は室町時代とも言われる日本発祥のもののようで、それほど目出度いと感じなくても良いのではと思っています。調べてみると、漢字の「傘」を分解すると「八」と「十」になることから「傘寿」は来ているようで、何とも権力者への忖度した祝いの臭いがします。それよりも、「傘寿」を前にして繰り返して考えるのは「認知症」のことです。
妻は「あなたは寝ていても考え事していて、突然起きてPCを立ち上げたりするのだから認知症にはならない」と太鼓判を押してくれるのですが、頭を使う仕事をしていれば認知症からは免れるというのは私にとって気休めでしかありません。「人が変わった」とか「違う人間になった」とかの風説に私は限りなく恐怖を覚えます。「暴言を吐く」とか「暴力的になる」と聞くと、私の周辺に認知症となった高齢者がいなかったせいか、本当に身の震えるほどの恐怖に囚われます。亡くなった父母も平均寿命以下の70歳代半ばで鬼籍に入ったので、体験のないことには人間の想像力は果てしなく膨らんでしまいます。きっと「パンドラの箱」を開けたような状態の人間になるのではと懼れます。あらゆるあらゆる邪悪な心、災厄や惨禍、不幸、不品行がその人間から飛び出して周囲の人間の穏やかな生活を根こそぎ奪ってしまうのではないか。たとえば戦地で善良な父親や善き夫が平然と人を殺めてしまうように人間らしさを失ってしまうごとく、認知症になると自分は豹変してしまうのではと想像してしまいます。「周囲の人間」と言っても妻しかいないのですが、小学生の頃を除いては、今が生涯で一番穏やかな日々を過ごしているだけに、その妻に失望されるのはとても恐ろしいのです。脳梗塞を患ってから脳の潤滑油と言われるDHCとEPA、それに物忘れに良いとされるイチョウ葉のサプリメントを服用していますが、飲まないよりはましだろう程度のまさしく気休めです。ともかく傘寿になってから、その先をどう生きるか考えようと思います。強面な見かけによらず、私は小心者で心配性なのです。「人は見かけがすべて」ではありません。