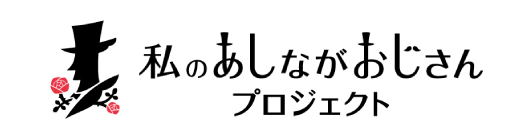Essay
エッセイ・連載
第24回 変わらない人、変われない人。― 時代の変化と連鎖する経営の自在性を考える。
2021- 「人間の家」の劇場経営をナビゲートする。
2025 年 07 月 03 日 (木)
劇場経営・文化政策アナリスト 早稲田大学文化推進部参与 衛 紀生
時代の変化を突き抜けて進むためにケインズから私たちが学ぶべきは。
「人間が一番難しいのは新しい考えを受け入れることではない、古い考えを捨てることだ」。
上記はケインズ経済学の祖であるジョン・メイナード・ケインズの言葉で、改革やイノベーションがいかに難しいかを体験的に述べたものと私は思っています。ケインズ経済学は、1936年に著した『雇用・利子および貨幣の一般理論』を嚆矢としていますが、ここでケインズが展開した経済理論は、近代経済学の父と言われていたデヴィッド・リカードが採用したことから当時は社会通念となっていた経済に対する考え方とは真っ向から相対するもので、彼の「古い考えを捨てること」の強い説得力になっていると私は思っています。ケインズを語るうえで私が好意的に感じるものがあります。第一次世界大戦後、敗戦国ドイツは連合国側とヴェルサイユ条約を締結します。 ヴェルサイユ条約ではドイツの 賠償金支払いが規定されて、その総額は、1320億金マルクと決定しました。 1320億金マルクは、現在の日本円にして約200兆円をゆうに超えます。 当時のドイツ国家予算の数10年分にもあたる金額でした。第一次世界大戦の犠牲者は、戦闘員および民間人の犠牲者の総計として約3700万人と記録されています。連合国側の意識は当然懲罰を加えるべき、しかも社会経済的に大混乱と打撃を与えたのだから厳罰を加えるべきとの社会の風潮と通念は動かしがたくありました。そのような空気の中で、ケインズは、法外な賠償請求を批判したことで有名な『平和の経済的帰結』の最終章で、経済学者としての矜持を示す見解を述べています。世界経済評論INPACTに掲載された小論文で関西大学商学部 高屋定美教授は以下のように記しています。「革命後間もないロシアを欧州につなぎ止めるには,ドイツ企業がロシア経済に介在する必要があると見ていた。すなわち,ドイツを経由し,経済制裁を緩和してロシアとの貿易が欧州経済復興に資するというケインズの見立てが示されている。第一次世界大戦後,欧州の平和が回復したとしても不完全な通商・金融体制は,欧州全体の経済復興を遅らせ,そのことが新たな対立の火種になることを危惧したのであろう」とケインズが当時は世界の常識となっていた社会通念に流されることなく、自分の専門性を信じて、その誇りを保持して「戦勝国の寛容さによる通商関係の再構築」こそが揺るぎない「平和」を招来させると主張しています。私たちはこのケインズの姿勢を見倣うべきと思い続けています。政治、経済、社会の変化と動向、とりわけ私は専門分野をマーケティングとしているので、企業戦略の動きにはしっかりとアンテナを張り巡らせています。そして、それぞれの専門分野から、障害となる囚われている常識やバイアス(特に無意識の先入観であるアンコンシャス・バイアス)を視界から排除して「ことの本質」に迫り、見極める専門的知見による「透視能力」は、とても重要であると、私は考えています。オーストリアの経済学者で、「イノベーション」、「アントレプレナー」、「破壊的創造」といった現在でも使われている経営学の言辞を生み出したシュンペーターは、1912年に発表した『経済発展の理論』の中で「新結合」(new combination)という言葉を使って「イノベーション」の概念を提唱しています。「新結合」(new combination)とは、「従来の常識では組み合わせたことのない要素を組み合わせることによって、新たな価値を創造すること」と定義すべきで、いわば「思い込み」や「常識」から離脱して、思いもよらぬものを結合させて「新しい価値を創造する」ことがイノベーションなのです。ケインズの言葉から、私はイノベーティブな意志を受け取ります。常識や思い込みの繭の中に閉じ籠っている保守思考からは、現状や未来の課題を解決に向かわせるイノベーションは決して起きないのです。
話は飛びますが、先日、東京藝術大学演奏藝術センターで年二コマの講義をしました。一コマ目は例年通り可児市文化創造センターalaの社会包摂型劇場経営の詳細と市民にもたらせた成果を述べたのですが、今年度からは『芸術経営の基礎知識』として、今後の急激な人口減少と経済的困窮に適合する新結合である芸術マーケット転換のためのマーケット・イノベーションの基礎となる知識を簡単に解説するために4本の論文を挙げました。マイケル・ポーター&マイク・クラマー『Strategy and Society(競争優位のCSR戦略)』 (2006年) 『Creating Shared Value』(2011年)、『コトラーのマーケティング3.0』(2010年)、井原哲夫氏の『愛は経済社会を変える』 (1995年)がそれで、その冒頭にセオドア・レビットの記念碑的論文『マーケティング近視眼』(1960年)の、自らの産業をどのように「事業定義」するか、その定義次第で産業が衰退化するとのレビットの指摘を学生たちに紹介しました。講義終了後、研究室に戻る準備をしているところに一人の学生が来てこんな質問をしました。この一連の講義は担当講師として文学座の座員が仕切りをしているのですが、「文学座を劇団と定義するのは間違いなのですか?」というものでした。私は瞬時に団体の使命である目的と手段を混同していて「事業定義」としては不適と判断しました。「演劇が人間にどのような変化をもたらすか、人間にとって演劇の果たせる機能を考えないと駄目だね。演劇はあくまでもそのための手段だから、『人間』をど真ん中に据えないと事業定義にならないね。レビットが例示したハリウッドの衰退が自らを映画産業と定義したところから始まったと同じだね」というような返答をしました。立ち話ですから、その返答で学生の腑に落ちたか否かは分かりませんが、疑問を解くための思考の舳先は提示できたと思っています。新著の『人間の安全保障としての文化芸術』を校了した頃に、たまたま劇団協の部会で「事業定義」についての問題提起を部会長であり、劇団協会長に投げたところ、「演劇をするために劇団に入ってきているのだから、その動機から見れば」と常識的な事業定義からテイクオフすることは難しいのではとの見解でした。劇団を選択したのはあくまでも出発時の動機であって、選び取った演劇というメディアの本質的な価値に錘を下ろして行く作業こそがアーチストとしても大切だと私は思うのですが、私はその「生産者主権」からの寄る辺ない返答にいささか失望して、それ以上は議論することを諦めて、その矛をただちに納めました。
アーチストの優位性は文化芸術業界の構造的欠陥。
演劇団体に限らず音楽団体も、アーチストの優位性が通常であって、それが構造的に芸術団体の経営面での甚だしい遅鈍の原因となっています。そもそも私は演出家や俳優などのアーチストに「経営」を委ねることには80年代から大反対でした。活用する能力がまったく異なっており、成果を生むために必要とされる知見は重なりようのないものだからです。マネジメントやマーケティングでアーチスティックな助言を必要とする場合は間々あるものの、現在進行するマイケル・ポーターとマイク・クラマーの歴史的論文を嚆矢とする、サービス価値と経済価値をともに両立させて、その相乗効果によって離脱者を生まないマーケットを形成する「社会経済収束性」(Socio-economic conversion capacity)に裏付けされた経営環境の大きな変化にアーチストがアンテナを張っておけなどと言うことは無理無体な「言いがかり」のようなものと、私には思えます。アーチストが客席の稼働率を考え、損益分岐点を設定して、最善なマーケティングを探るなどは本末転倒で、アーチストは創造性を育み、研鑽することに専念すべきです。それが出来る環境を整えるのが経営に携わるスタッフのミッションです。とは言っても、ある米国のカンパニーで、生きた馬を出したいという演出家とそれだと想定予算内に収まらず馬は俳優が箒にまたがって観客の想像力に委ねれば知名度のある演技陣をキャスティング出来るという経営側と衝突したことがあり、その選択をアーチスト(演出家)に迫っているのを見た、と仄聞したことがあります。当時の日本ではありえない力関係でしたが、私は経営に携わる者として、当然ではないかと思った記憶があります。カンパニーを組んでいる以上は、その持続継続性をすべての面で考慮するのは負わなければならない大きな責任であり、いかにアーチストであっても治外法権的な特権は認められるべきではありません。仮にその作品創造に公的資金が導入されているならば、その「特権」は、さらに制約を受けるべきと私は考えています。
30代初めまで、週刊誌に2本、月刊誌3本の劇評を抱えていましたが、安い原稿料で生活費さえ覚束ない生活環境で、月に二回ほど参加していた研究会や学会への参加のための旅費交通費、資料渉猟のための書籍代などはどう足掻いても夢のまた夢だったため、広告宣材製作のプロダクションでアートディレクターやコピーライターとして糊塗をしのいでいた時期があります。その頃の旧友で小さな広告代理店を経営している者から「企業広告と明示しないと売り上げが20%くらい上がる」という話を聞いたことがあります。広告代理店のマーケットに関する近年の感覚だそうです。生活者をかたまりとして捉えるマスマーケティングが、80年代に入ってから価値観の多様化によって「分衆」という言葉が現れ、「顧客志向」が企業戦略として支持されて、顧客ニーズにそったなかば注文販売のようなカスタマイズ化が一般的になります。それでも「生産者主権」を手放そうとせず、一見すると「消費者主権」なのですが、実態は商品・製品とサービスの品質による差別化が出来ない時代環境のなかで、顧客に対しての向き合い方の変革は弥縫策にとどまっていたと総括せざるを得ません。価値の多様化で「顧客が何処にいるか」「どのような受取価値を訴求しているか」が見えにくくなっているのに加えて、2000年代に入ってからは、価値観はさらに細分化されるようになります。そのことで2010年前後からCX(カスタマー・エクスペリエンス)を高める目的で顧客進化(カスタマー・ジャーニー)の全体像を把握して設計するために、たとえばCokeの自販機にアプリケーションを組み込んで、顧客像をデータとして取得しようとする「アプリマーケ3.0」と言われる時代に入っていくことになります。さらに2015年あたりになるとビックデータを活用して、デモグラフィク・データ(年齢、性別、収入、学歴、職業など、個人の属性に関する客観的で具体的な情報)とサイコグラフィック・データ(個人の価値観、興味、ライフスタイル、態度、性格、購買履歴など、より主観的で心理的な属性に関する情報)をAIで解析して潜在的顧客にアプローチする「パーソナライズドマーケティング」が登場することになります。しかし、これは個人情報保護法に抵触する可能性があって、確かに「アプリマーケ3.0」より一歩も二歩も踏み込んではいるものの、このアプリの販促ウェブサイトには必ず法に抵触しないようにとの但し書きが付せられています。この「パーソナライズドマーケティング」は、フィリップ・コトラーの最新刊『H to Hマーケティング-人間中心マーケティングの理論と実践』で痛烈に批判した「利益至上主義のマーケッターの行き過ぎた非倫理的行動により、(中略)マーケティングのイメージは近年悪化の一途を辿っている。大半の人は『マーケティング』と聞くと、『嘘』『欺瞞』『ごまかし』『迷惑』『操作的』といったネガティブな言葉を連想する」と舌鋒鋭く言い放った「数量信仰」に憑りつかれている、「数量信仰」の呪いから醒めていないマーケッターたちの産物であると、私はいまさらながら呆れています。ガルブレイスが1950年代の米国の大量生産大量消費を観察して、「依存効果」という概念を提起した『ゆたかな社会』は、いま読むと企業は商品やサービスへの所有欲求の充足のみならず、消費者の満足感まで供給しているという「巨大な消費社会」への彼の冷静で皮肉なまなざしを感じます。にもかかわらず、現代のマーケッターたちは、ガルブレイスのまなざしを共有できずに、一世紀ものあいだ白日夢に囚われて右往左往しているのです。自分の使命を深掘りせずに、多くの数量さえ囲い込めれば最良のマーケティングをまっとうできたとの上辺をなぞっただけの思い込みに囚われていることに滑稽ささえ感じます。
マーケティングの常識を疑う。
戦後の50年代に飛躍的な経済成長を果たして、世界に冠たる大消費型国家と社会を短期間で成立させた様子を観察したガルブレイスは、歴史的名著『豊かな社会』で「企業の生産活動は製品やサービスのみならず、それらを消費したいという欲望も作りだしている」とのバンドワゴン効果とかデモンストレーション効果という「依存効果」の概念を提起しました。これを販売スキルとして定着させたのが米国型の「マーケティング」なのですが、そのマーケティングも社会環境の推移にしたがって変化しています。「数量信仰」に囚われたままの古色蒼然たるマーケティングは、近年の「社会ネットワーク理論」に着目した社会経済学によって意味を減衰しつつあります。その理論に依拠して、「ある製品やサービスの価値が利用者の数量に依存している」との「ネットワーク外部性」という新しい依存効果が唱えられるようになっています。新著『人間の安全保障としての文化芸術』で指摘したように、従来からのマーケットの定義は、「相互価値交換関係」であり、需要量と供給量が一致するところを均衡点の創出といい、そのときの経済的価値である価格を均衡価格と言って現代の経済学では「価格は需要と供給の両方によって決まる」と考えられ市場は経済的・金銭的価値の均衡によっています。しかし、近年では社会ネットワーク理論を裏付けとして経済的・金銭的価値に限定されず、社会心理的価値や社会経済的価値に着目する加重インパクト会計への傾斜が優勢となってESG経営やパーパス経営においては、新しいマーケットの定義がなされつつあります。
その価値の変化をロジック化したのが、競争優位の経営戦略の大家マイケル・ポーターと社会貢献コンサルタントのマイク・クラマーによって「ハーバード・ビジネスレビュー」に2006年と2011年に発表された2本の論文『Strategy and Society(競争優位のCSR戦略)』及び『Creating Shared Value(共創価値創造の戦略)』です。前者では、従来からの社会的責任経営(CSR)は善きことではあるがボランティア派遣とか寄付に終始していて企業の収益を費やすだけで、もっと企業にとって戦略的であるべきとの提言であり、後者はそのロジックをさらに前進させて、従来は「経済的価値」と「社会的価値」はトレードオフ(二律背反)とされている「常識」からテイクオフして、経済利益と社会課題の解決を一体的にともに追求することを求め、かつ両者の間に相乗効果を生み出そうとする企業と消費者の価値の共創と共有によるCSV経営(共創価値経営)という「新しい扉」が開かれます。これは、「地動説」から「天動説」への転換ほど、企業経営と私たちが携わるアーツマネジメントの基本ロジックを大きく揺さぶることになりました。あわせて、ポーターの研究者である慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授岡田正大教授が研究知見として「社会経済収束性」(Socio-economic conversion capacity)という経営概念が知見として提示されます。まさに「経済利益と社会課題の解決を一体的にともに追求することを求め、かつ両者の間に相乗効果を追求」する経営手法が広範にわたって、しかも急速に影響を拡大しています。
フィリップ・コトラーとジョアン・シェフ・バーンスタインの共著『STANDING ROOM ONLY』(立見席のみ 未邦訳)には、ニューヨークで、大人数所属のオーケストラと少人数編成のアンサンブル楽団が共同して経営戦略に特化するホールディングスのような(米国の法律に不案内で「ような」としか言えない)事業体を持って、各楽団はそれぞれの事業運営に専念して経営効率の向上や戦略の実施は迅速化できているという事例が挙げられています。これは、文化芸術団体が構造的に抱える組織課題の解決法の一つとなると直感した憶えがあります。変化に脆弱な文化芸術界は、サバイブのための準備を怠ってはいけないと考えます。
すぐそこに来ている人口減少によるマーケットの縮小の危機。
人口減少による各マーケットの縮小については、いまから危機回避策を準備しておかなければなりません。国立社会保障・人口問題研究所による総人口が1億人を割る時期が2056年と前回推計より3年後ろにずれ、そのペースは「わずかに緩和」したとの報告がなされました。その要因は在住外国人の存在で、いまからおよそ20数年後の2048年には9913万人になるという。計算上はすべてのマーケットは25%~30%程度の縮小が見込まれます。「社会ネットワーク理論」の外部性は、「ある製品やサービスの利用者が増えることで、それらの価値全体が向上する」というものですが、当然ですが「負の外部性」もあります。そうなるとただでさえ小さい文化芸術マーケットは、前掲程度の縮小では済まないのではと、私は強く危惧しています。80年代から信じ込まれていた「良いものを創れば人は集まるという単純で、不合理な集客論」の業界内常識や思い込みを即座に脱ぎ捨てて、科学的なマネジメントとマーケティングに裏付けされた経営にただちにシフトすべきと私は考えます。
しかし、「文化芸術推進計画」(第2期)を策定した前期の文化政策部会では、当初の(案)として文化庁ウェブにアップされた文言には、「人口減少は、文化芸術の担い手のみならず公演の鑑賞者や博物館・美術館の入館者等の減少にもつながり、需要の減少・市場の縮小が見込まれる。今後は、地域間格差にも配慮した文化芸術振興方策を進めるとともに、マーケットインの発想をもって活動することがますます重要となっている」との愚策とも言える対策が記されています。この対策として挙げられた「マーケットイン」に私は強い違和感を持ちます。1950年代の米国で、地域の劇場が急速に映画館となったことで、若い演劇人たちとニューヨーク大学の学生が立ち上がった「リージョナルシアター運動」は、興行街ブロードウェイの価値観に一極化されて演劇自体の多様性が担保されないとの危機感からの大きなうねりとなったのも「マーケットイン」が背景となっていたことを忘れてはいけません。しかも、「芸術水準の向上」という政策目的の指標として観客動員数というアウトプットを設定していることに私は唖然となりました。簡略して言えば、観客動員数が多ければ「芸術的評価」は高くなる、ということを意味している指標設定です。「マーケットイン」のレトリックの背景にあるのがこの指標設定だとしたら噴飯ものと言えます。誤解の第二は、マーケティング(marketing)とセリング(selling)との古典的な混同です。セオドア・レビットの定義によれば、Sellingは商品やサービスを金銭に換えたいという売り手のニーズに依拠したものであるが、Marketingは、買い手の、何らかの問題解決をしたいという買い手のニーズが中心となる概念、となります。「マーケットイン」は、明らかに宮田前文化庁長官が安倍政権に忖度して到底東京藝大前学長とは思えない不用意に言い放った「稼ぐ文化」の政策的継承だと私は断じて疑いません。それは「金銭に換えたいという売り手のニーズに依拠」しているからです。
コロナ禍以降の社会は、何もかもが大きく、しかも瞬く間に変化する時代となっています。「VUCA(ブーカ)の時代」と言われています。「VUCA」というのは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった造語です。一言で表せば「先の読めない時代」です。昨日まで信じていた考え方を、その根底から疑ってみないと前に進めない、そればかりか意思決定したことさえも僅かなあいだに陳腐化して破棄しなければからなくなる時代環境です。そのような時に「変わらない人、変われない人」というのは、淘汰されるのを座して待つ存在となります。そのような人物の関わる企業組織は、必然的に急速な衰退化が現実となります。「VUCA(ブーカ)の時代」では、自分自身を加速度的に変化させる自在性が求められると、私は思い続けています。