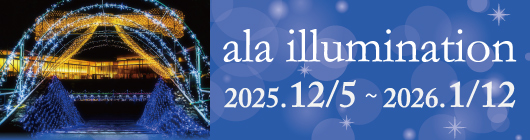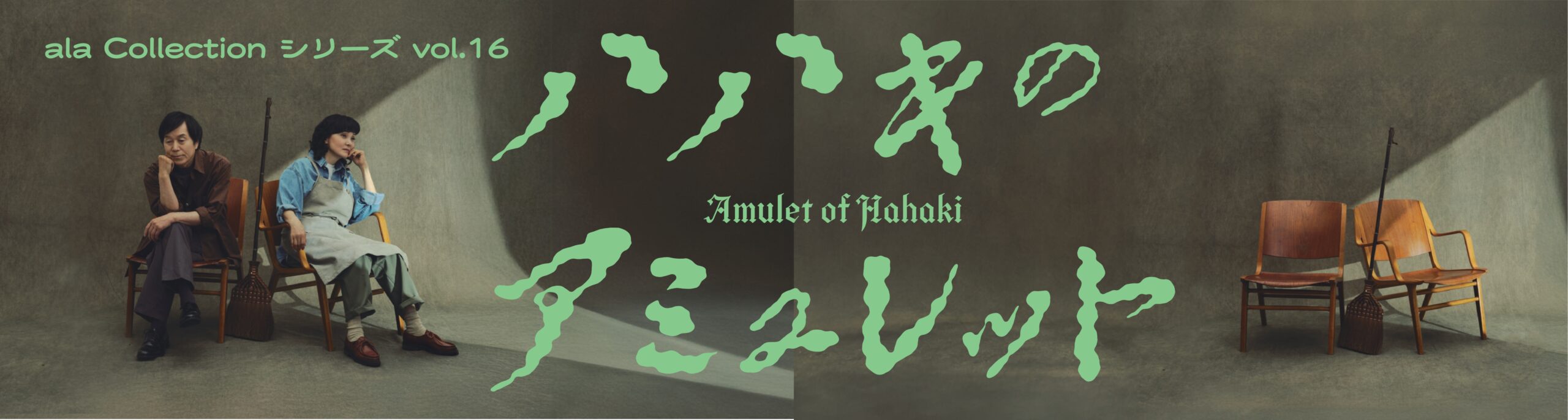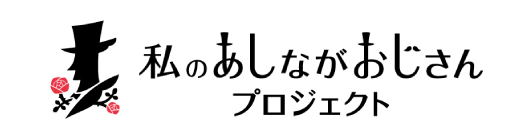Essay
エッセイ・連載
第22回 「欲望」をコントロールできない人間が不幸を世界に撒き散らしている。―選挙の季節に考えて、思いをめぐらせたこと。
2021- 「人間の家」の劇場経営をナビゲートする。
2025 年 03 月 01 日 (土)
可児市文化創造センターala シニアアドバイザー 衛 紀生
遅くとも昨年11月には出版する心積もりで進めていた『人間の安全保障として文化芸術―人間の家・その創造的アーツマーケティング』が、編集サイドのウィルスによるシステムダウンが6月に起こって遅延は免れないことを出版社から知らされました。文化審議会に設けられた文化政策部会と文化経済部会の政策立案をになう委員会の動向と、あわせて政治経済及び社会の環境の急速な変化は、先行き不透明なVUCAの時代にあって目まぐるしく変化して、その変化にも即応する内容にしなければと、加筆をしないと先行きを見通すものとならないと7月末から8月、9月初旬まではPCの前で全体を俯瞰しながらの作業に日々追われていました。もともとは物書きでしたので、その時間は達成感で充実していたのですが、横目でいくつかの「選挙」を、いささかストレスを受けながら見ていました。
プーチン、ネタニヤフ、トリはトランプ。ストレス源勢ぞろいの憂鬱な近未来。
一番のストレスフルだったのは米国大統領選の推移でした。それ以降に、ウクライナ軍事侵攻を始めたプーチンと、パレスチナ・ガザ地区で正当性のない爆撃を繰り返して、戦死者のうち国連人権高等弁務官事務所発表によれば確認された死者の7割近くが女性と子供だったという事態が明らかになりました。その戦闘を主導するネタニヤフも私にとって大きなストレスの発生源です。加えて、トランプが大統領になったらかなわないなという気分でした。上記の三人になぜストレスを感じるかは、一国の指導者でありながら、世界を俯瞰せず自身の「欲望」をコントロールできない人間だからです。トランプ政権は前回同様、「パリ協定から離脱」を表明しました。あわせて、「WHO」(世界保健機関)からの脱退もにおわせています。近い将来に森林開発と氷山や凍土の氷解によって発生すると予想される新しいウィルスによるパンデミックもありうるとされる中で、「中国の人口は我々よりはるかに多いが、WHOへ支払う金額はとても少ない」と拠出金の多寡で再検討の可能性もある、との表明をしています。コロナ禍でワクチン開発に大きな役割を担った米国疾病対策予防センター(CDC)を正しく評価せずに、自国民を生命の危機に晒す判断を「拠出金の多寡」で決めてしまうという軽率きわまりない意思決定をしようとしています。パナマ運河、グリーンランドへの領土的野心のためには、経済的・軍事的手段をいとわないとの発言には、ただただ呆れるばかりです。近視眼的で幼児的な「イヤイヤ期」なみの人間が大国の大統領になっていることに失望するばかりです。
米国民がどうしてこんな男を大統領にしているのか、それも尋常ではない熱狂をもってと、私は考え込んでしまいます。そうこうしているうちに大統領令へのサインが始まって「ダイバーシティ」(多様性)への全否定にトランプのサインがされたのを見て、「民主主義が属人的に否定される」封建領主の所業を間近に目撃して、この「米国社会の分断」が癒えるのには少なくとも100年はかかるだろうとの絶望感の中に私は居ました。ロスの大火災をバイデン失政によるものと発言して、数日前に起きたアメリカン航空と軍のヘリの大惨事に対しては、知的障碍者や精神障碍者か「ジョー・バイデン前大統領とバラク・オバマ元大統領の政権下で、連邦航空局(FAA)の航空管制官の採用基準が引き下げられたことが、悲劇の一因」と言い放っています。このような発言をためらいもなく発する大統領の国が「偉大な国」とリスペクトを受けるとでも米国民の半数が信じているのだろうか。2年後の中間選挙で少なくとも「トリプルレッド」は解消できるかもしれないが、心に住みついてしまった「価値観」や「倫理観」はそう簡単に変わることはない。「社会の分断」は、確実に経済にも悪影響をもたらして共同体の劣化となります。
「少数与党」は、国会と政治を見える化する国民の選択
米国大統領選とともに気になっていたのは、自民党総裁選と衆議院の総選挙でした。新自由主義との訣別を前回の総裁選で口外して「新しい資本主義」を唱えながら、安倍一強時代の後始末に成果を出せずにいた岸田首相が「裏金問題」で立ち往生して、9人の候補者で争われた自民党総裁選を横目で見ながら、誰が総裁になれば何がどのように変わるのかを見極められずに、恥ずかしながら加筆を進めながら遠見の見物をしていました。結果はご承知のように、高市早苗議員を僅差で振り切って石破茂議員が新総裁に選出されました。これで、国会で議論すべき重要案件を閣議決定で決めてしまった「安倍一強時代」の総括の第一歩にはなりそうだとの予感を持ちました。しかし、マスコミ論調は、そのあとすぐに行われた総選挙の結果を含めて、何も決められない「少数与党」と「党高政低」との大合唱でした。私はそういうジャーナリズムの見識の低さに心底から呆れました。彼らは政府が機能不全に陥って、政治の不安定化がすぐにでも現出して日本の政治が破綻するとの「常識」という制度や仕組みが過去の経緯や歴史に呪縛されている「経路依存症」から抜け出せないでいる、と私は思いました。決選投票で敗れた高市議員が新総裁からの党三役入りを請われながら固辞した結果、石破新総裁は、歴代最長の4年の国会対策委員長を務め、対論激論を調整する能力を必要とされる総務会長も経験している森山裕議員を幹事長に配しました。調整型と言っても、選挙区の先輩議員にあたる自民党税調に君臨した山中貞則氏のような剛腕型の調整役ではなく、足して二で割る調整に長けている幹事長を石破新総裁は任命したと言えます。明らかに安倍派を中心とする党内右派との「調停役」としての幹事長職だと私は当初から見ていました。総裁選後の衆院選の実施時期も、下馬評での小泉進次郎優勢に党内世論が傾いていて、「石破総裁」を想定していなかったからで、総裁選の時に言っていた「予算委員会後に衆院選」を実現できなかったことは党内をまとめられていないというマスコミ論調こそが事実を見誤っていたことを物語っていました。ジャーナリズムの「常識」は、与党で政策合意をして、それを国会に上程して反対するしかない野党という構図、つまり「経路依存による政治の安定でしかないことが白日の下に晒された、と私は考えています。
自民公明の与党合意ですべてを決めていて、あとはその合意にそったかたちで政策決定を多数決で決めていた国会軽視の実態が破綻して、少数与党という存在が与野党の調整を公開する、つまり「見える化」することで国民から遠くなっていた政治と国会を国民に近付けることになった、と私は考えています。「野党は反対ばかり」の一般論、特に若年層の民主主義に対する懐疑的な考えは、それにより選挙での投票率の相対的な低さを結果していると私は思っています。政権発足後のマスコミ挙ってのネガティブキャンペーンの結果、石破内閣の支持率は、「10月3日実施の前回調査(46%)より15ポイント減の31%でした。不支持率は前回調査(37%)から13ポイント増の50%で、支持率を逆転した」(毎日新聞・社会調査研究センター)との記事になりましたが、あれだけ従来からの「常識に呪縛されたジャーナリズム」のキャンペーンを展開すれば、当然の支持率の低下と不支持率の上昇となるのではないでしょうか。石破政権に相対的には好意的と思える毎日新聞でさえそのような記事になるのですから、みずからの非を認めない、正義を自認するマスコミによる論調では、石破政権は早晩行き詰まるとなっていました。支持率・不支持率は、朝日新聞でもNHKでも、ほぼ同じような動きとなっています。
ところが、右派に好意的な産経新聞社とFNNが12月の予算委員会開催中に調査した結果は、内閣支持率が45.9%となり、11月の前回調査の43.8%から2.1ポイント上昇し、不支持率は前回比2.1ポイント減の47.7%で、同調査の政党支持率では自民党は28.1%と内閣支持率を大きく下回っています。この数値が何を意味するのかは明らかです。「経路依存症」に囚われているジャーナリズムの「少数与党」と「党高政低」との危機意識が見当違いであるとの現われです。「石破首相の言動が変化した」との言説は、自分たちの認識を正当化するたぐいの欺きでしかありません。私は、地元の和多理神社境内での総裁選出馬表明から一貫して民主主義への姿勢は変わっていないと思っています。古いタイプの引退した政治家かが大連立を進言しましたが、もはや彼の志向は化石レベルであり、国民の求めている民主主義政治ではありません。私は米国民の癒しがたい「分断」に比べて、日本の民主主義は、清和政策研究会(安倍派)の一強時代と比べて、はるかに民主主義の体を取り戻していると評価しています。大分ましになったと思っています。解決に向かわせなければならない社会課題は「人権」「気候変動」「災害対策」「種々にわたる格差」等々山積していますが、見える化する国会と政治が機能することで、米国と比較すれば相対的に民主主義の綻びのリスクはシュリンクして「欲望」がコントロールできて国民に近いところで意思決定が可能となるのではと期待してやみません。
2015年1月の「館長エッセイ」に、私は『劇場は人々を幸福にできるか ― 岐路の年の初めに思う』を書いています。前年の12月14日の総選挙が「米国型の格差社会に向かうのか、それとも新自由主義的経済の横暴と強欲に立ち向かう社会の在り方に向かうかの『日本の岐路』になると考えていました。しかし、「59.32%の戦後最低の投票率となって、しかもとりわけ若い層の投票率が20歳~24歳で35.30%、25歳~29歳で40.25%、30歳~34歳で47.07%と5割を割り込んでいることに脱力感を否めませんでした。失望感さえ感じました」と日本の近い将来を担う世代の低投票率には愕然としました。「政治なんて誰がやっても同じだから」、「政治は良く分からないから」、「投票したい人がいないから」というのが彼らの棄権の主な理由だと仄聞しました。自分たちの生活をより良くしようという意志の放棄です。極端に言えば、為政者にそのような白紙委任をする態度は、独裁的な考えの持ち主の政治家にとって都合のよいことになってしまいます。「社会包摂を掲げて劇場を経営する身としては、「無力感と脱力感と、劇場人として何とか突破口は考えられないかを反芻する年末になりました」と書き継いでいます。
2023年は私にとって忘れられない年となりました。館長として、文化政策研究家として、劇場経営の当事者であり研究者として、大切な3人の「伴走者」を相次いで失った年でした。そのうちの一人であった栗田康弘は、長野市民芸術館からアーラに移って、社会包摂型劇場経営の中核である顧客コミュニケーション室長として「あーとま塾」の事業担当責任者となって次のような言葉を遺しています。「今回久しぶりに集った3人の仲間たちとのセッションから、劇場にせよ、映画館にせよ、商店街や食堂や喫茶店や駄菓子屋にせよ、あらゆるパブリックな場とは、その専門性を語る以前に、その場を愛する人たちの〈つながり〉と〈想い〉を育む一つ一つ大切な居場所でもあったのだと改めて気づかされました。それを多くの人たちが忘れてしまうくらい豊かな時代が少し長く続いて下り坂に差し掛かった今、いつの間にか小さくて大切な居場所が消えてしまっていたことによる人々の更なる孤立化が、じわじわと大きな社会システムの良質な部分まで蝕んできている気がしています」と、私たちが「大切なもの」からはぐれてしまっていることへの危機感のにじむ文章を書いています。亡くなったあと、私は栗田家の遺された皆さんに、人間に優しい「栗ちゃん」のアーラでの仕事ぶりをしたためて、彼の生き方を記憶にとどめて、忘れないで生きてくださいとのメッセージを送りました。そして、癌は発症していましたが、亡くなる3年前に「可児市文化創造センターalaのビジネスモデル(2020/5/18 栗田イメージ)」と題したPDFイメージ図をあずかりました。彼が如何に自分の仕事と使命を誇りに思っていたかを物語っているものでした。
「豊かな時代が少し長く続いて下り坂に差し掛かった今、いつの間にか小さくて大切な居場所が消えてしまっていた」のくだりを読みながら、政治と国会への信頼が急速に低下した平成8年の衆院選での投票率の低下を、そして、その前の参院選では何と45%を割ってしまったことを思い出しています。繰り返しますが、この傾向は政治と国会での政策決定のプロセスが「密室化」したことの結果だと私は考えています。国民と政治が著しく乖離してしまったのです。「一強他弱」時代には国会での論議を省いて閣議決定だけで政策が決められてしまったことまでありました。彼の危惧していた「いつの間にか小さくて大切な居場所が消えてしまっていた」のは、経済や政治の動向が知らぬ間に社会に大きな変化を生んでいたということではないか。この90年代半ばから始まったバブル崩壊後の政治不信は、一挙に高まっています。長い間、年間の自殺者数は2万人台で推移していたのが、この時期を境に1998年度になると突如として3万2863人に跳ね上がって、それ以降は3万人台で高止まりして社会問題となっていました。それでも、その解決を政治と国会に委ねようとの動きは顕在化しませんでした。この「政治や国会と国民生活の断絶」を根本的に解決しなければとの動きは出て来ませんでした。この頃の自殺者は、経済的問題を抱えた中高年が中心でした。彼らの社会的孤立と孤独は政治で解決できる問題でありながら、「自己責任論」によってその声は封じ込められる空気が社会を覆っていたことを思い出してください。「少数与党」は、国会と政治を見える化する国民の選択です。その結果、国民との甚だしい距離にあった国会と政治が「見える化」に向かっているのです。どこまでも情報公開することで、政治と国会は、私たちの生活に身近な制度となると私は考えています。
現在政治課題となっている「高額療養費」「高校学費の無償化」「社会保障費の軽減化」等々も、そのプロセスを透明にして所得制限を設けるよりも、従来からの「応分負担」から自己責任論の出ない「応能負担」にシフトする時代的必然があるのではないでしょうか。「いのちの格差」「教育の格差」等のあらゆる格差を最小限にする政治的努力をしてこその政治への信頼を取り戻すことになると私は考えます。そうすることで「いつの間にか小さくて大切な居場所が消えてしまっていた」ということはなくなりはしなくても、最小限に止められるのではないでしょうか。私は日本はもはや階級社会化していると思っています。経済的な分断は国民生活を注視すれば明々白々です。福祉、医療、教育の諸制度に「所得制限」を設けることは格差を拡大することを意味する社会になっていると考えています。現場からの発想がいまこそ大事なのではないでしょうか。栗田が遺したビジネスモデルからも、その立場を守るべきと感じています。