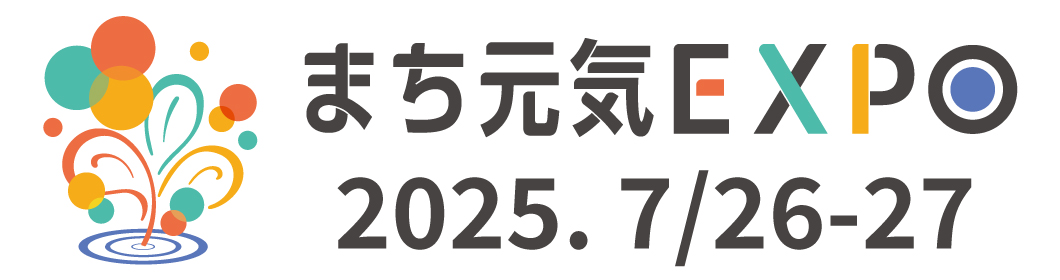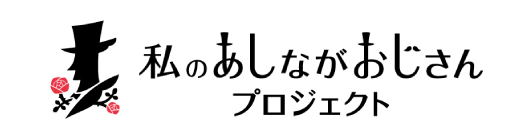重要なお知らせ
ウェブサイトリニューアルのお知らせ
News & Topics
ニュース&トピックス
2025 年 4 月 5 日
2025 年 4 月 1 日
2025 年 4 月 1 日
2025 年 3 月 31 日
2025 年 3 月 28 日
2025 年 3 月 26 日
2025 年 3 月 20 日
2025 年 3 月 17 日
2025 年 3 月 15 日
2025 年 3 月 13 日

Events
みる
この場所でしか味わえない没入感
日常から離れ、目の前で生み出される
多彩な表現を全身で体感ください

Join
さんかする
多様な講座やワークショップから
興味のあるものを選んでご参加を
新しい刺激、出会いがあります

Use
つかう
習い事の発表や仲間と集う場所に
アーラの施設群をご活用ください
初めての方は気軽にご相談ください

About ala
アーラについて
私たちアーラは、芸術の殿堂ではなく
人々の思い出が詰まった「人間の家」
生きる活力とつながりを生み出します