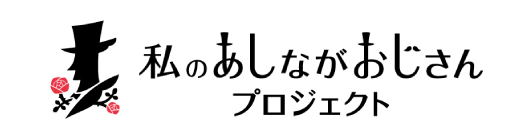Essay
エッセイ・連載
第25回 老いるということ、「認知症」のことが気にかかる年齢になった。社会包摂経営は手段でしかない、多くの人々の寄り集まる劇場を ― 「顧客満足度」と「顧客幸福度」、マーケティングの定義の二極化。
2021- 「人間の家」の劇場経営をナビゲートする。
2025 年 09 月 21 日 (日)
-
劇場経営・文化政策アナリスト 早稲田大学文化推進部参与 衛 紀生
はじめに 公共劇場職員は「花よりも花を咲かせる土になる」姿勢を。
可児市文化創造センターalaの館長に就任した2008年から13年間、隔週の月曜日に、シフト制の関係で日に2回開講して来た「館長ゼミ」で、私は「政治や経済や社会の動きにアンテナを張っていなければ社会包摂型経営はできない」と繰り返し言い続けてきました。「生きにくさ」や「生きづらさ」を感じている人たちや子どもたち、障害を持っている人たちが「生きる意欲」を持つためには自己肯定感をもたらす他者との関係づくりが大切であるし、それには文化芸術の協働性が強い力を発揮すると思っていたからです。文化芸術の知識は、仕事で必要とされるし、職務を通して学んでいけばよいとの基本的な考えが私にはあります。この13年間で文化芸術に関したテキストは、フィリップ・コトラーとジョアン・シェフ・バーンスタインの共著『芸術の売り方』(原題 Arts Marketing Insights)だけで、中心となったのは、「ハーバート・ビジネスレビュー」のマネジメントとマーケティングに関連する論文を教材にしていました。そもそも90年代に次々に開設された高等教育機関におけるアーツマネジメント学専修課程で「経営」に関連する講義があまりに少ないことに私は常々疑義を抱いていました。文化経済学会の学会誌に掲載された『日本のアーツマネジメント研究とその実践における課題と問題点』という論文でその問題点を書いています。2005年のことです。その頃の全国の高等教育機関のアートマネジメント学科、専修コース、加えて教養選択科目として設置されていたところまで含めると47大学にもなっていました。ただ、カリキュラムを俯瞰すると専門分野と認識されていた「芸術教養」に偏っていて、本筋であるべき「経営管理」についての知見を養う講義のプライオリティは明らかに低位にありました。不必要とは思いませんが、演劇史や音楽史が現場で必要になる喫緊性はありません。したがって、館長ゼミはマネジメントとマーケティングに寄せた教材となりました。その知見を持つことで、政治・経済・社会の動向に機敏に反応できる公共意識の高い人材を育てようと考えたのでした。新著『人間の安全保障としての文化芸術-人間の家・その創造的アーツマーケティング』にも文化芸術関連の記載が少ないとの評はありますが、それは公共的なすべての市民を視野に入れた場を創造するための力を持つ職員こそが必要との現場での実感があったからです。今回は、政治経済の指導者から日々の暮らしに窮している者までが全身を染め抜かれているGDP信仰を俎上にのせて、生きる者にとって幸福感のもてる日々を得るためにGDPに代わる指標とは何かを考えてみました。時代の価値観は、HappinessからWell-beingに流れを急速に速めています。その変化の中で、劇場サービスの指標も「顧客満足度」から「顧客幸福度」に移行しているのではないだろうか。現下の価値観の変化を好機ととらえて国籍・性別・障害の有無などにかかわらず、すべの人々が違いにかかわらず劇場を人々にとって安心できる「生命維持のプラットフォーム」として、近い将来起こるだろう人口減少と可処分所得の減少と税収減へのリスクヘッジとして機能するデザインのひとつとして近著を補完する意図をもって提案したいと考えています。また、そのような場である劇場を実現するために政治・経済・社会への観察力が公共劇場の職員には必須との従前からの前提から来ているものとご理解いただければ幸甚です。本稿は、近著を補綴するとの位置づけで書いておきたいとの思いから書き下ろしています。
文化経済学会での出来事とニューエコノミクス財団のこと。
7月5日・6日に京都橘大学で開催された文化経済学会研究大会で、会員企画として「『常識』にとらわれない公立劇場の経営―日本の文化政策・ 自治体文化行政 ・創造都市・劇場経営の観点から捉え直す」と題されたセッションが設けられました。創造都市研究家の佐々木雅幸先生、自治体行政研究家の中川幾郎先生、そして私という顔寄せで、私の記憶するかぎりこの3名がパネルとして並ぶのは初めてのことでした。私は近著『人間の安全保障としての文化芸術』について創造都市分野、自治体行政のお立場から肩に力の入らない談論風発の鼎談を楽しみたいとの希望はあったものの、そこは学会の研究大会ですので、私を含めたパネル全員が各々PPによる短めのプレゼンテーションは用意してセッションは始まりました。私は10数年続けている東京藝術大学演奏藝術センターでの年2コマの講義のPPを編集してプレゼンしました。通常はアーラの社会包摂型劇場経営の基礎的な考え方と実装事例で十分に受講者に伝わるとしてプレゼンをしていましたが、今年度からは2コマ目にセオドア・レビット、マイケル・ポーター&マイク・クラマー、フィリップ・コトラー、井原哲夫先生の研究知見を「芸術経営の基礎知識 What is Marketing and Management?」として、新たなPPを作成していました。その一部を流用して、最後に新たに英国・ニューエコノミクス財団の「人間の幸福研究機関」(Centre for Well-Being) の創設者である統計学者のニック・マークスの『The Happiness Manifesto』(しあわせ宣言)からのダイジェストのシートを1枚加えたもので、まだまだ今後深掘りしなければならない課題が山積している研究テーマです。ちなみに『The Happiness Manifesto』は、ニューヨークの非営利団体TED(Technology Entertainment Design)からキンドル版のみ発行されていて、私はナンシー・フレイザーの『資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのか』とともに取り寄せの注文をしました。少し時間は必要としますが、深掘りに入ろうと思っています。マーティン・セグリマン博士(ペンシルバニア大学の「ポジティブ心理学」の学績資料とあわせて、やりがいを感じる未来に向かう作業となりそうです。
私がニューエコノミクス財団の存在を知ったのは、2017年の世界劇場会議国際フォーラム『劇場は社会に何ができるか、社会は劇場に何を求めているかⅡ~日本版 社会的処方箋は可能か? 』にパネルの一人として英国から招いたウエストヨークシャー・プレイハウス(WYP :現リーズプレイハウス)のアーツデベロップメント(芸術による社会開発)部の職員ニッキー・テーラーの発言「国のシンクタンクであるニューエコノミクス財団の2018年の報告書の一節「他者を助けることに関心がある人たちは幸福度が高い傾向にある」でした。彼女はWYPの誇る高齢者プログラム「ヘイデイズ」の責任者であり、近年は認知症プログラム、難民プログラムの開発実施も担当しています。ニッキーの言っていた「他者を助けることに関心がある人たちは幸福度が高い傾向にある」は、1994年に岡山県立美術館でアートファーム岡山の大森誠一氏の司会進行で開催されたシンポジウムで初めて温めていた劇場によるまちづくり構想を「創客」という言葉で提案した時から、その所与の条件としていた「利他性による社会的価値」を内包している社会心理学のエビデンスです。
「経済成長が人間を幸福にする」という信仰への痛烈な不信感とニック・マークス。
すぐに「ニューエコノミクス財団」を調べるとニック・マークスという人物に行き当たり、GDPの向上が人間の幸せをもたらすという「GDP崇拝」への彼の感じている不信感に強く共感しました。「なぜ我々は国家システムの成功を『国民の幸福と福利』ではなく『国の生産性』で語るのか」との私たちへの問いかけは、私の常識に突き刺さる鋭利なものでした。「豊かさの本質」はGDPや生産性でははかれない、とニック・マークスは喝破しています。近著『人間の安全保障としての文化芸術』に記したように、この経済指標の考案者であるサイモン・クズネッツは、大恐慌時のフーバー大統領の依頼でこの経済指標をつくることになりますが、クズネッツは当初、軍事費、投機的取引、有害物質を撒き散らして環境汚染を配慮しない産業収益等は、「国民の豊かさ」にとってマイナス要因となり算入しない姿勢でしたが、次の大戦への備えとなる指標を得たい政権の政治的思惑から、彼の提案は退けられます。しかし、クズネッツは、1934年の連邦議会上院への報告で、この経済指標の数値は、「GDP指標の数値が国民の『豊かさ』や『幸福感』を表す『社会厚生指数』ではない」との警告を発しています。その報告書の中で「私たちは(一見確定に数値化される)国民所得計算(GDP)に対しても、(略)幻想を抱きやすく、誤用もしがちだ」とその欠陥を鋭く指摘しています。クズネッツにとっては、国の経済を計測することは国民生活の豊かさを計測することとイコールでなければならないと考えていました。彼の考えでは、軍事力は国民の豊かさと結びつきません。あわせて「本来意図していない社会的・政治的問題解決のために指標が使われ始めたなら、単純な概数に対する崇拝が大きな問題を引き起こす」との懸念も合わせて述べています。しかしクズネッツは論争に敗れ、1942年、軍事支出も含んだ数字としてアメリカのGDPが初めて公表されることになります。当時の大統領は第二次大戦時に異例の4期の長きにわたって政権を掌握していた、任期中に大統領の権限で他国に武器や軍需品を売却、譲渡、貸与することができる「武器貸与法」を成立させたフランクリン・ルーズベルトでした。政治的争いの結果、GDPという経済指標は、政府が支障なく財政政策の運用ができるデータの作成となり、戦争を見据えた政府側の現実路線が勝利して、クズネッツは断念を余儀なくされました。仮にトランプ大統領の日本に向けられた防衛費要求GDPの3.5%に応えると、およそ「21兆3250億円」が日本の国民総生産に積み上げられるのです。これをどう思いますでしょうか?「21兆3250億円」が日本で生活している人々の幸福感に本当に結び付くでしょうか?
「創客経営」の萌芽の経緯。
文化芸術の「社会的・公共的価値」を梃子として、一部の愛好家のみを対象としているマーケットを変えなければ、当時のホール建設ラッシュはハコモノ批判と税金のムダづかいとのマスコミからの批判を受けて社会を挙げての総意となって文化芸術と国民との距離は開くばかりだとの危機感が私には強くありました。ほとんどの劇場ホールは地方債発行を当時の自治省から認可されて、建設総経費の90%弱は元利とも地方交付税交付金で手当てされて、自治体の自主財源はなんと10数%で良かったという事情があっての90年代の「ホール建設ラッシュ」でした。むろん事業予算は自主財源で賄わなければならないので、オープン記念の杮落としにはなけなしの予算は積むのですが、2年目からは貸館が中心となって閑散としてしまうのが通常でした。当然のことですが、「文化芸術と国民との距離は開くばかり」で拱手傍観していたら酷いことになると杮落とし公演に招待されるたびに思っていました。とりわけて私の専門領域だった演劇は特別な存在としてあまり認知されていない分野で、当時は演劇を前面に押し出した公共劇場は、女優の村松英子さんが初代芸術監督に就任していた倉敷市芸文館しかなかったのですが、私の裡は「何かしなければ」という焦りでいっぱいになっていました。そのような折の1994年、劇団離風霊船の長野県・岡谷市での日本における早い時期のアーチスト・イン・レジデンス(AiR)による舞台製作合宿があり、当時としては珍しい市民参加劇『「誕生」するなら』で、宿泊はバンガローの並ぶ小高い丘のキャンプ場でしたから、まちなかのスーパーや商店に買い出しに当番が出掛けて調理するという毎日でした。当然、舞台製作に参加した市民ばかりではなく、食料品を購入した店の人たちとも劇団員との交流が起きます。その後の離風霊船の東京での公演に出掛けると、岡谷で見知った市民の皆さんと親交をあたためることが度々ありました。その岡谷滞在と前後して、私は日経新聞の連載コラム「やさしい経済学」に強い関心をもって、著者である慶応義塾大学のマーケティングの碩学井関利明先生(元日本マーケティング協会会長)のマーケティング理論の根幹をなす「リレーションシップ・マーケティング」の考え方に強く惹かれるようになります。また、90年代になろうとしている頃、来るべきインターネット時代を先取りするマーケティングについての一冊であったドン・ペパーズとマーシャ・ロジャースの共著『ONE to ONEマーケティング』を井関先生監訳で出版されて、日経のコラムも『ONE to ONEマーケティング』も、マーカーと朱線だらけになるほど読み込みました。のちにその頃のインスパイアを振り返って、連載していたVS局長の第72回に『商店街の八百屋の親父のように』という原稿を書いています。私の見聞きして来た商店のリレーションシップマーケティングとITによるONE to ONEマーケティングには、リレーションシップを結ぶことでサービスのカスタマイズ化して、体験を共有して価値を共創してつながりを強化し、離脱しにくくなるという共通点があると思ったのでした。それは離風霊船と岡谷市民とのあいだにある「つながりの質」、商店街の店のおやじと顧客との「つながりの質」とは同質であり、共通性があるリレーションシップであり、生きたマーケティングとして学んでおり、その発見は私にとって大きな出来事でした。
しかしながら、私の頭の中から前述したホール建設ラッシュが文化芸術と国民のあいだを親和的なものとするより、かえって文化芸術と生活者たる国民との距離に取り戻せないほどのへだたりを生じさせてしまうのではとの危機感は厳然としてありました。悶々としながら評論家として毎日の劇場通いをしているうちに、上記したリレーションシップ・マーケティング、とりわけてFace to faceで培われる「つながり」の強固さと、前年の93年に体験した長崎の障害児たちの「のこのこ劇団」とのインパクトある出会いがつながり始めました。学習障害による社会的な不協和を演劇的手法で問題ないものにしていく「のこのこ劇団」のプログラムに私は強い衝撃を受けました。社会的・公共的価値をコミュニティで共有することで文化芸術の存在意義の認知を背景とする「創客」の経営概念が私の裡で次第に首をもたげ、ゆっくりと立ち上がってくるのを感じていました。同年岡山県美術館での、アートファーム岡山代表の大森誠一氏の進行するシンポジウムで、上記した経緯から受けたインスパイア、すなわち福祉・医療・保健・教育の課題解決へ向かう文化芸術の社会的公共的価値を基盤としたリレーションシップ・マーケティング(関係づくりマーケティング)による文化芸術の社会的認知の獲得を企図する「創客経営」を課題提起することになります。これが、97年に上梓した『芸術文化行政と地域社会: レジデントシアターへのデザイン 』の第一章と第一項のタイトル「カキの森の文化政策」と「芸術支援から芸術による社会支援へ」につながり、可児市文化創造センターalaの「社会包摂型劇場経営」に至るのです。
国民を欺く経済指標、GDP成立の政治的背景。
「ニューエコノミクス財団」のニック・マークスは、ほとんど宗教のごとく熱烈に信じ込まれているGDPを経済指標とする「経済発展が私たちを幸せにする」という思い込み=常識に深い疑問を感じていました。そして、2006年に「地球幸福指数」(Happy Planet Index)という指標を公表しました。これと前後して、フランスの二コラ・サルコジ大統領は、2008年に「経済業績と社会進歩の計測に関する委員会」を設立しました。巷間言われる「スティグリッツ委員会」です。世界的な経済学の碩学であるジョセフ・スティグリッツを座長として、同じくノーベル経済学賞の厚生経済学のアマルティア・センをはじめとする米・英・仏・印からの25名の碩学を集めた委員会で、その報告書の中でサルコジは「私には強い確信がある。それは、経済業績を計測する手法を変えない限り、われわれの行動は変わらないだろう、という確信である」と記して「世界中で人びとはウソをつかれている、こうした数字は偽りだ、自分たちは操られていると信じている。人びとがそう信じるのには十分な理由がある。長年の間人びとの暮らしはますます苦しくなっているのに、生活水準は向上しているのだと教えられてきた。これではだまされていると思うのが当然だろう」と激しい言葉で「GDPはまやかし」と断じています。「GDPは仕組まれた虚構」であると結んでいるのです。ニック・マークスとスティグリッツ委員会がGDPを批判の俎上にあげたのは偶然ではないと私は考えます。ミルトン・フリードマンを旗頭とする新自由主義経済思想は政府の介入である規制を緩和し、排除してあたうかぎりを市場原理にゆだね、機能させてこそ経済発展を生むと、ひたすら国力を向上させようとする経済思想です。主語は「国家」です。ニック・マークスやジョセフ・スティグリッツやアマルティア・センたちは、主役はあくまでも「人間」であり、「国民」であると考えています。ミルトン・フリードマンとは考え方が真逆なのです。私はクズネッツがGDP計測の要素に「所得再配分機能」を組み込まなかったために「国力」の計測指標が揺るぎないものとなってしまい、誤解と錯覚をもたらしたと考えています。
私の知るかぎりでもっとも早い時期にこのGDP崇拝の問題に触れているのは、1968年のカンザス大学でのロバート・ケネディの講演です。そこで彼は「私たちは余りにも長い間、物質的な蓄積を、人が持つ素晴らしさや共同体の持つ価値よりもはるかに優先させてきた。(中略)GNPには人生を価値あるものにするものは一つも入っていない」とクズネッツが最後までこだわった国民の幸福感と、一般的に信じ込まれている経済指標との著しい乖離を鋭く指摘してます。ちなみにGNPは93年まで使われた経済指標でGDPは国内で一定期間内に生産された付加価値の合計額。 日本企業が海外支店等で生産した付加価値は含みません。現トランプ政権の閣僚は富裕層と超富裕層で組まれており、最近の連邦議会で僅差で成立した減税案「大きく美しいひとつの法案」は、メディケイド(低所得者向け医療保険制度)については新たな就労要件を課し、また同制度の財源を確保するため、病院などに課税する各州の権限を制限します。米議会予算局(CBO)の試算によると、こうした変更により、米国では2034年までに1180万人が医療保険を失う恐れがあるという。また、低所得者層の食料品購入を支援する「補助的栄養支援プログラム(SNAP、旧フードスタンプ)」にも新たな就労要件が導入されることになっていて、新自由主義経済の広く行き渡った国のかたち、倫理性の欠如する経済的・社会的ダーウィニズム(Darwinism)を当然とする優勝劣敗の米国社会の行き着く先がこの法案だったのではないだろうか、と私は思っています。半世紀前のロバート・ケネディの危惧が着々と現実になっていると考えます。メディケアやフードバンクに予算を投じるという「再配分」機能により社会の不平等を是正する考えは冷酷にもここでは排除されています。
クズネッツの断念を継承するBeyond GDPの動きの高まり。
しかし、私は絶望していません。米国・ビジネスラウンドテーブル(BR)が2019年8月19日に発表した声明に、館長席のPCの前で思わず声を上げてしまいました。ビジネスラウンドテーブルは、日本で言えば「経団連」や「経済同友会」のような議会や党に対してロビーイングのための組織と機能を持っています。その実効性はにわかには信じられないとの論評はありましたが、アップル社からウォルマート社まで、米国の主要企業が名を連ねる財界ロビー団体の企業トップ181人の署名の入った「企業の目的に関する声明」(Statement on Corporate Governance 企業統治に対する宣言)は、次のように締めくくられていたのです。「どのステークホルダーも不可欠の存在である。私たちは会社、コミュニティと、国家の成功のために、その全員に価値をもたらすことを約束する」と、新自由主義の「株主資本主義」から本来の「ステークホルダー資本主義」に回帰する強い意志が、そこには明確に書き記されていました。それを遡る2008年11月には、欧州委員会、欧州議会、ローマクラブ、OECD、WWF(世界自然保護基金)によって、「Beyond GDP」の国際会議が開催されて、進歩を適切に評価し、豊かさを計測する指標を構築する取り組みが行われています。Well-beingが人間の安全保障にとって重要であるとの認識の急速な広まりによって、いずれこのような評価指標の改革の動きは出てくるとは思っていましたが、予想通りに社会民主的な傾向のある欧州が動き始めました。私が声を上げて驚いたのは、新自由主義経済によって格差分断を生じさせながらも繁栄を享受している米国内からBeyond GDPの動きが、しかも経済指導者たちから出るとはまったく考えていなかったからです。この動きに対して総務省のウェブサイトには「GDPを拡大させることを目標に各種政策が行われてきたが、主に生産量を計測する目的で作られたGDPでは、人々の生活の質がどれくらい向上しているかといった豊かさ(Well-being)や、将来に利用できる資源がどれだけ残っているかといった環境面を十分に評価できないことから、GDPを超えた評価指標を示して、これを政策目標にしていくことが必要となることが認識されている」と解説されています(太字筆者)。日本でも「顧客幸福度」を提案しているスタートアップのコンサルティングであるファンベース・カンパニーは、「2023年のG7広島サミットで『ウェルフェア(幸福)を追求する経済政策』が提唱され」、「自社の利益追求だけではなく、『商品やサービスを通じて、いかに顧客を幸せにしているか』『いかに従業員が幸せに働いているか』といった顧客や従業員の幸せを考慮した経営のあり方は、今後ますます求められていくと予想されます」とその時代的確信を記しています。
これは歴史を振り返れば、1934年の連邦議会上院への報告で、「このGDP指標の数値が国民の『豊かさ』や『幸福感』を表す『社会厚生指数』ではない」と発言したクズネッツの警告と断念を受け継いだものと位置づけられます。上記の総務省の解説で太字で記した箇所は、ニューエコノミクス財団のニック・マークスの提起している評価指標である地球幸福度(Planet Well-being Index)と符合しています。つまり、ポジティブ心理学の知見にしたがえば、「Well-being」は、身体的、精神的、社会的に良好な状態を持続できる存在の幸福感であり、他者との関わりやつながりや共感共生の状態と考えられます。GDPという指標の無効性に対してBeyond GDPを主張しているというよりも、国の生産力と国民の幸福感の乖離が甚だしくなって、社会厚生指標で社会の在り様をはからないと実態が見えてこないとの意見が大勢を占め始めているということと、私は理解しています。その風潮が企業の持続継続性を重要視するCSV経営やESG経営、パーパス経営の存在に連なっていると考えています。日本での新自由主義経済思想は、アカデミア界隈では、中曽根政権での国鉄民営化に始まるというのが定説になっていますが、国民生活に直結するのは「聖域なき構造改革」のスローガンで施行された小泉政権下での労働基準法と労働者派遣法からだと私は思っています。簡単に解雇でき、それに年齢制限を加味して、金銭で合法的に処理できる法制を施行することで、企業の側は「コンプライアンス」(法令遵守)を免罪符にして格差を助長するありさまでした。小泉政権における「聖域なき構造改革」は、その後の政権にも引き継がれていました。現在喧しい「石破おろし」は、この新自由主義による政権運営の負の遺産による自民党政治への不信感によるものでです。参院選敗北だけではなくその中長期にわたる政権運営を総括しないかぎり、党への支持基盤を回復に向かわせることは難しいのではと私は思っています。まさしく「石が流れて、木の葉が沈む」ほどの時代環境の激変の時を私たちは生きているとの自覚を持たなければ前へ進めないのです。前に進めないばかりか、後退を余儀なくされると考えます。サイモン・クズネッツはノーベル経済学賞を受賞している経済学者ですが、私は彼の指し示した「クズネッツ曲線」をはじめて知った時に「なんて楽天的な」と思いました。「経済発展の初期段階では経済成長によって所得不平等が拡大するが、経済発展の後期では成長によって格差が縮小する」という彼の理論を曲線であらわしたもので、私自身のGDP信仰に対する不信感は、その彼の楽天的な考え方にとてもついていけないとの感想を持ちました。
トマ・ピケティとジョセフ・スティグリッツから「”えせ資本主義”」の行き着く先を考える。
クズネッツの「警告」からおよそ80年後の2013年に、豊かさと格差という世界が抱え込んでいる社会経済課題に、まったく別の角度からのアプローチがフランスの経済学者トマ・ピケティから提起されました。多くの人間が注目して話題沸騰した『21世紀の資本』がそれです。アマゾンの売上総合1位になって、経済学のみならず社会学等の関連する研究者や諸現場に携わる人間がこぞって購入したのではないかと思わせるほどでした。翌年に邦訳版が出版されて、私もご多分に漏れず早速取り寄せましたが、その大冊ぶりにいささか怖気づきました。Well-beingを考察するうえでも不可欠と思われる学績であるとの確信はあったのですが、のちのニック・マークスの仕事にもつながる労作であり、とりあえずは『週刊東洋経済』と『エコノミスト』を月に2回程度東京に戻る折に品川駅構内の三省堂ブックセンターで購入してタイパに走りました。ピケティは、産業革命後の19世紀末から約200年にわたる経済統計と指標を収集して分析しており、それが900ページを超える大冊にしているのです。彼が提示したことの中で最も重視すべきは、資本収益率(r)が経済成長率(g)を上回る傾向(r > g)により、格差が拡大しているとの指摘、すなわち(r > g)であると私は思っています。これは「資本主義という制度」が宿命として孕んでいる「宿痾」が格差の拡大の原因であり、その自己利益のみを追求して他者をかえりみない、残念ながら人間が生来持っている「欲望」を制御するための政策によって補綴と補整をしなければ世界は弱肉強食の社会的ダーウニズムによる社会の不安定化が進むというとの結論です。資本主義の下では本質的に経済格差の拡大は何らかの手を打たないかぎりは不可避という主張です。「資本主義の富の不均衡は放置しておいても解決できずに格差は広がる。 格差の解消のために、なんらかの干渉を必要とする」というのがピケティの導き出した結論であり、「何らかの干渉」とは、国際的な累進課税制度の施行と公正な運用が彼の政策提案です。
そのピケティに対して、世界的な経済学者のジョセフ・E・スティグリッツは、『世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠』(原題The Great Divide)でいささか偏りのある次のような見解を述べています。「私から見るとピケティの認識は、問題の深刻さにかんしては正しいものの、原因と対処法にかんしては必ずしも正しいとは言い切れない。もしも、アメリカ人が彼の本から間違った教訓を得てしまったら、不平等問題に本気で取り組むさい、必要な変化を起こす障害となりかねない」と、彼自身が目の当たりにしている「今日のアメリカの実態は、不平等を創出すべく設計された”えせ資本主義”と説明するほうがぴったりくる」と資本主義自体の制度的宿痾と、米国内の暴走する新自由主義経済思想(”えせ資本主義”)を綯い交ぜにしてしまっています。私にとって、ジョセフ・F・スティグリッツはジョン・メ―ナード・ケインズとともに、経済学の自身の知見から現実の人々の生活に襲いかかっている諸課題の解を求めようとするアカデミシャンのあるべき正しい姿勢を持っていて、研究者の末端にいる私として敬意を持っている存在です。そのスティグリッツがピケティの「資本主義の宿痾」と米国内の現実を支配している「”えせ資本主義”」を別のフェイズと分けて考えられないことに、私は少なからずの衝撃を受けました。彼は「血迷っている」と咄嗟に感じました。ピケティの学績を考える際に最重要なのは「資本収益率>経済成長率」の不等式であり、その解消のための処方箋をたとえ仮説であっても提起することではないだろうか。
「血迷った」とは感じたのですが、世界的な経済学者であり高く深い知見の持ち主であるスティグリッツが、何故ピケティの業績に対して、その素顔に怒りをむき出すような反応をしたのかを考えて、彼を弁護しておかなければならない必要を私は感じています。彼が自身の研究者の誇りをほとんど顧みずに「”えせ資本主義”」とのいささか不規則な言辞を記したのには、新自由主義経済の「教祖」たるミルトン・フリードマンと、目の前で急速に融けていく米国社会への想像を絶する危機感があったからだと私は思っています。そのフリードマンが右派経済学の拠点として牛耳っていたのがシカゴ大学でした。スタッフォード大学からシカゴ大学に転じた若きスティグリッツは、年少の頃から数学に長けていたので当初は物理学を専攻していましたが、社会の不平等の研究に数学をどう活用するかという宇沢弘文教授の課題意識に強い関心を寄せて、研究の深化に心を砕いていた姿に強く惹かれ経済学に転じたと東洋経済のインタビューに語っています。宇沢弘文教授とは、すべての人々が豊かな経済生活を営み、優れた文化を展開し、人間的に魅力のある社会の安定的な維持を可能にする自然環境と社会的装置を指して、それらは国家による官僚的な支配や市場原理による利潤追求の対象とされるべきではないという経済概念である「社会的共通資本」(Social Common Capital)を提起した、私が敬愛する賢人です。ちなみに文化芸術は社会的共通資本の3分類のうちの制度的資本に数えられており「人間的に魅力のある社会の安定的な維持を可能にする」社会的装置とされています。後年スティグリッツは、リンダ・ビルムズの共著『The Three Trillion Dollar War』 (邦訳『世界を不幸にするアメリカの戦争経済 イラク戦費3兆ドルの衝撃』)を、宇沢先生にこそ見ていただくべきだと思ったと告白しています。その本は、アメリカが参戦した、必要のない破壊的な戦争に対して、経済学者がどのように声を上げることができるか、ということを書きつづったものです。その内容を適切に評価してくれるのは宇沢先生以外にないと思う、とインタビューで語っています。彼が「”えせ資本主義”」と言い放った新自由主義は、1970年のニューヨークタイムス・マガジンにミルトン・フリードマン自身が投稿した『The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits』(企業の社会的な責任は利益の創出である)で提唱された「企業の第一の目的は所有者(株主)に対する経済的な利益の創出にある」、「格差や環境といった社会的問題は政府に任せ、経営者は株主利益の最大化に専念すれば、結局は富の総量が増えて社会のためになる」とする「株主資本主義」の発火点です。「福祉国家」の「大きな政府」に行き詰まっていた先進国政府は、GDPの伸長と経済発展の手段として、さらには高度成長期に翳りの見えた経済界も、「人間個々人の幸福感」から「国家の経済発展」を主人公とする新自由主義に雪崩をうって走ります。
この投稿が、それ以降の半世紀にわたって世界と人々の人間の尊厳と人権を蹂躙して格差と分断を生む経済思想の発端となります。その世界観によれば、商売で肝心なのは商売(the business of business is business)であり、経営責任者はその商売で利益を極大化することにのみに意識を集中すべきだ、ということが「経営の常識」とされるようになるのです。米国内では、スティグリッツが度々使う「テック・オリガキ―」(巨大なIT系企業)の自由が拡大再生産されて、大多数の国民が搾取される側に押しやられ格差の拡大が取り返しのつかない状態となると新著『資本主義と自由』に書いています。トランプ政権下では「テック・ライト」や「テック・リバタリアン」との言辞までが盛んに使われて、彼らが政治に及ぼす影響への批判も表面化しています。インタビューでスティグリッツは「フリードマンらが提唱した理論は、自己の利益を追求することが社会的満足度を向上させるとした、アダム・スミスの言葉を反映しているようにも思います。自己の利益の追求というと貪欲であれ、と言っているようで、貪欲であることはよいことのように聞こえてきます」と市場原理主義は欲望を全肯定していると批判しする一方で、『スティグリッツ 資本主義と自由』で経済的な自由は政治的な自由と公平の問題と強くつながっているとの認識を示しています。「本来、経済学は高度に政治的な学問でもあるはずだ。アダム・スミスの時代にはこの二つの学問は切り離されてはいなかったが、現在では、経済学者と政治学者は互いの言語が理解できなくなっている。もう一度経済学と政治学をつなぎなおし、新自由主義の何がどのように適切でなかったのか、きっちり説明する必要がある」と主張しています。経済が政治に従属してしまった今日の時代環境の不毛さを嘆いており、彼が言い放った「アダム・スミスは死んだ」の背景は、ウォールストリートへの波状的なデモがなされていた時期に発刊された『世界の99%を貧困にする経済』(原題The Price of Inequality)の第3章「政治と私欲がゆがめた市場」を読むとよく理解できます。先のインタビューで彼は「私たちはどのような社会を作り、どのような人になりたいのか、よく考えなければなりません。私たちは本当に、経済学(の前提とされる)に自己中心的な『ホモ・エコノミクス(経済人)』になりたいのでしょうか」とあとから来る者たちに問いかけて、「研究者はこれまで起きてきたことを具体的に理解することを助け、また政治的な制約や、何かを売り込もうとしたり、特定の利害に動かされる者たちから自由」であり、「私たち研究者は、社会の幸福に本当の関心を持った、数少ない存在なのです。私たち研究者が共通の目的に向かって協力して取り組んだとき、初めてこの新しい世界は作られるのです」との研究者の現実のもとでの社会的役割と公共的使命をメッセージとして述べています。
倫理性の欠如が他者との関係不全にまで及ぶ決定的欠陥。
資本主義に「欲望の自由放任」という非倫理性を組み込んだフリードマン思想へのスティグリッツの危機感は、第二次トランプ政権の閣僚のうち13名が超富裕層で占められているというかたちで現前化します。『世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠』での彼の危惧は、まぎれもなく現実となっています。トランプ政権は「一つの大きくて美しい法案」と名付けられた大型減税法案を法律として成立させました。これにより、低所得者や障害者向けの公的医療保険「メディケイド」の予算は今後10年間で9300億ドル(14兆円)の大幅削減となり、議会予算局の試算では、今後約1200万人の米国民が保険を失うとされています。新法ではこのほか、低所得者層の食料品購入を支援する「補助的栄養支援プログラム(SNAP、旧フードスタンプ)」の要件厳格化によって、議会予算局は利用者が320万人減少するとしています。法人税率下げと所得税の減税競争と累進性の失速による格差の修復不可能な極大化と国民の分断は必至です。「超富裕層」の人間にとって日々の暮らしに艱難辛苦している人々の気持ちを自分事とする考えは絶対にありません。スティグリッツの危機感は、米国民が等閑視している間におぞましい現実となったのです。
岸田前首相の総裁選の時に言い放った「新しい資本主義」とは何だったのか、いまでも考えます。あるいは、「石破おろし」の動きを前にして、仮に岸田前首相の危機感による政策的大転換がなされていれば自民党は地盤沈下による地滑り的敗北からは逃れられたのではとも考えています。前首相は、総裁選の折に新自由主義的な経済政策を改めて、「成長と分配の好循環」を実現する経済政策を高らかに掲げて「新自由主義からの脱却」を主張し「新しい資本主義」を謳って国民に期待感を持たせましたが、多様な格差による社会の改善へ転位の最後の「蜘蛛の糸のような期待」を岸田首相はものの見事に裏切ったのではないか。その折の政策パンフレットには、キャピタルゲインへの増税案が書き込まれていました。『1億円の壁』の打破を訴えたのです。総裁選で所得額1億円以上の富裕層の所得額が大きくなるほど税率が下がる「1億円の壁」の解消を打ち出したわけです。給与所得は累進制で住民税も含めて、最大55%の税率がかかるが、金融所得は一律20%なのです。富裕層は金融所得を多く持っており、年間所得が1億円を超えると所得税の負担率が大幅に下がるというのがその考えのもとにありました。ところが足元の日経平均の続落と安倍政権から続いていた貯蓄から投資の政策にさおさすものであり、激しい集中砲火を浴びてあっさり撤回してしまいました。資本収益率(r)が経済成長率(g)を上回る傾向(r > g)により、格差が拡大しているとのピケティの指摘から学び、その資本主義の内包する宿痾を構造的に修正するなら、それがたとえ「石が流れて、木の葉が沈む」という常識を外れていることであったとしても、「返り血を浴びても」進めるべきだったと私は考えます。「新自由主義的な経済政策を改める」とはそういうことです。むろん、完全無欠で完璧な資本主義なぞ存在しません。長い歴史の中で時代環境の変化の中でその都度改変されてきた訳で新自由主義経済思想も、その時代の要請で改変された一ページに過ぎないのですが、しかし、政治的指導者、経済的指導者ばかりか、大衆庶民にとどまらず低所得の生活困窮層までが全身を染め抜かれてしまった「資本主義の改変」による格差と分断から私たちは抜け出せる道はあるのでしょうか。
「地球幸福指数」とポジティブ心理学の知見。
「ニューエコノミクス財団」の創案した指標である「地球幸福指数HPI(Happy Planet Index)は、毎年大規模な世界的講演会「TED Conference」(テッド・カンファレンス)を開催している非営利団体での講演でのニック・マークスの下記のモチベーションによるものと思われます。
「私たちの社会の進歩を計測する指標は、あらゆるものを測りますが、人生を“生きる価値のある”ようにするものは測れません。(中略)驚くことでもありませんが、世界中で人々は、自分自身や子ども、家族やコミュニティの幸せを望んでいます。お金は、幸福や愛ほど重要ではありません。われわれはみな、誰かから愛し愛されることを望んでいるのです。お金はまた、健康ほど重要でもありません。みな、健康で充実した暮らしを送りたいのです。これらは人間が自然に持つ願望です。ではなぜ、統計学者はこれらを計測しないのでしょう?」
「生活者としてのニック・マークス」の素朴な疑問と「統計学研究者としてのニック・マークス」の専門分野の視野の広さが弁証法的に止揚された、前回のエッセイで書いたケインズと類似する思考回路をこの講演内容に私は感じます。そのようなモチベーション起点に考え出されたのがHPI指標です。「ウェルビーイング」「平均寿命」「国内格差」の三つを足して、人間の社会的活動によって消費される資源量や排出される二酸化炭素量と、地球が生産する資源量と吸収する二酸化炭素量のバランスをスコア化した「エコロジカル・フットプリント」(人間活動が地球環境を踏みつけにした足跡という意味)で割ることで、人間が本来あるべき姿で、自然と共存共生しながら生活している本来のあるべき人間の姿が導き出される、との考えからHPIは設計されています。この「エコロジカル・フットプリント」を指標の設計要素に加えることで、地球という資源に負荷を与えているか否かを計り、人間の生命維持の持続継続性からHPIを算出して、パーソナルな幸福度にとどまらない、未来とつながり、環境の将来を展望する指標となっています。
ポジティブ心理学では、幸福度を上げる5つのポイントとして日々の生活で私たちの出来ることを以下のように整理して示しています。
- つながる(Be Connect):人とつながる、コミュニティの一員となる、自然とつながる
- アクティブになる(Be active):生活実感に行動的な思索をする習慣をつける
- 好奇心を持つ(Take notice):季節の移り変わりや疑問を持つ瞬間を喜びとする
- 学び続ける(Keep learning):やったことのないことに挑戦する、新しい考えに触れる
- 与える(Give):何かしらの「いいこと」をしてみる、他者に利することをする
が5つのポイントです。
この5つのポイントは、ペンシルベニア大学ポジティブ心理学センターのマーティン・セグリマン博士の創設したポジティブ心理学のウェルビーイングの為の5つの構成要素PERMAとほとんど重なっています。PERMAとは、ポジティブな感情(Positive Emotions)」「Engagement)」「関係性(Positive Relationships)」「人生の意味・意義(Meaning)」「達成(Accomplishments)」の5つです。また、セグリマン博士は、PERMAが成立してWell-beingとなるための心構えを次の3点と記しています。❶Well-beingに貢献すること、❷他の価値(地位・金銭)を手に入れる手段としてではなく、それ価値自体を追求すること、❸他の要素とは独立して定義され、測定されること、を前提条件としています。博士は、Happinessのみの追求は厳しく戒めていましたが、Well-beingに貢献する要素としてポジティブな感情を重要と考えています。それは彼が「学習性無力感」や「学習性絶望感」を専門分野として研究していたことと無縁ではありません。失敗や壁にぶつかることは「学びの機会」であり、前向きにそれらを捉えることが、そのあとに控える「意味・意義(Meaning)」「達成(Accomplishments)」と深く関連する「Engagement)」には諸論ありますが、私は使命と手段の歯車が噛み合っている「夢中になっている状態」「充実している状態」と理解しています。一般的なEngagement意味の「約束・契約」とは離れますが、機械工学用語に歯車が噛み合うというのがあります。いかにも「我を忘れるほどの充実」の意は充たし切っているではないでしょうか。「Positive Relationships」は、博士がWell-beingの高度化のためにもっとも重視している「社会的人間関係」を指していて、良好な人間関係は当事者が孤独や孤立していないことを証しているからです。「Meaning」は、社会・政治・家族・宗教・芸術などの自分より大きな何かに対する奉仕者としての立場(ministrant)を指していると思われます。その奉仕者の立場から改善や変革や自己改革を成し遂げてWell-beingの状態が自他を問わず達成できたことが「Accomplishments」です。その結果というよりプロセスに焦点を当てた価値であると言えます。セグリマン博士はHappinessを「感情的で一瞬しか継続しない幸福感」、Well-beingを「身体的・精神的・社会的に良好な継続する幸福感」と定義しています。また、ホジティブ心理学では、金銭や地位などは「地位財」とされて持続しない幸福感のHappinessに分類されます。したがって、欲望の自由放任による非倫理的な手段によって獲得した金銭的価値は、Happinessであるかも知れないが、決してWell-beingに到達できた証しとは考えられていません。
顧客満足はHappiness? 時代環境の変化からWell-beingへの傾斜が強まる。
ラルフ・ネーダーという米国人の名前をご存知でしょうか?
私たちの世代が中高生の頃に「消費者運動の旗手」として世界中の耳目を集めた人物です。当時の米国社会は、ガルブレイスが著書『ゆたかな社会』によって「依存効果」の概念で解き明かした巨大な消費社会がつくった繁栄の矛盾が噴き出始めていました。当時のケネディ大統領も暗殺される前年に『消費者の利益保護に関する大統領特別教書』を公表しているほど生産者主権の横暴による解決しなければならない社会課題が次々に浮上していました。そのような時代背景から「顧客満足」(Customer Satisfaction)という語彙がマーケティングの世界に生まれて、生産者やサービス供給者には金科玉条のようになります。合衆国消費者問題局の「アメリカにおける消費者苦情処理」調査を2年にわたって、そのリサーチを担当したジョン・グッドマンが「顧客満足」の嚆矢とされています。「グッドマンの法則」と呼ばれている「苦情に迅速に解決することが出来ると、リピーターになる」等の「クレーム処理は、顧客維持の機会」との考え方は、現在ではカスタマーセンターの設置等で常識となっていますが、顧客満足研究の第一人者で(社)消費者関連専門家会議の設立者の一人、初代専務理事兼事務局長、顧問を歴任した佐藤知恭氏によって「グッドマン理論」はまとめられ、集約されたものが巷間に流布されたと私は理解しています。
顧客満足度を経営戦略として体系化したのは、「新規顧客獲得」に走りがちの経営戦略の誤りの根拠を示して、既存の顧客の維持に傾注すべきと「顧客ロイヤルティ」の概念を提起したフレデリック・F・ライクヘルドではないかというのが定説になっています。ライクヘルドは、ベイン・アンド・カンパニーに入社して『コンサルティングマガジン』誌の2003年6月号で、世界で最も影響力のあるコンサルタント25名に選ばれた民間の凄腕マーケッターです。彼は代表的な著作である『ロイヤルティ戦略論』をはじめ、『顧客ロイヤルティのマネジメント: 価値創造の成長サイクルを実現する』『「顧客愛」というパーパス』といった、「顧客ロイヤルティ」と「顧客満足度」に関する実践的経営理論をやつぎばやに上梓して提起しています。彼の理論で有名なのは「1.5の法則」と「5:25の法則」です。「1.5の法則」とは、新規顧客に販売するコストは既存顧客を維持するコストの5倍かかるという法則で、「5:25の法則」とは既存顧客維持の販売コストは新規顧客開発より低いので、顧客離れをたった5%改善するだけで利益に25倍と大きな影響が出る、という理論です。これは、Customer Relationship Managementの手法で、日本語では「顧客関係管理CRM」と訳されています。つまり、「顧客満足度」を算することで、CRMを行う際に必要な消費者の基盤構築をすることが可能となって、顧客離脱を最少にする成長戦略と戦術を実行すべき、というのがライクヘルド理論の概括と考えてよいでしょう。また「顧客ロイヤルティ」がブランディング効果を高め、バズ・マーケティングにより多くの人にブランドの価値を届ける重要な存在となるとの意味で「アンバサダー効果」とも言われることがあります。
2016年に世界劇場会議国際フォーラムをさいたま市文化センターでも開催しようと動いていました。関東以北からの若い人たちが可児にまで来るのは過負担になると数年前から考えていたからです。その件の初交渉でさいたま市文化センターを訪れた折に、センター職員から「公演事業は概ね好評です。満足度は94%ですから」と言われて、「それはアンケート集計でしょ」と観客のアンケートを信じ切っていることを訝しく思ったことがあります。鑑賞事業での回収率20%台のアンケートほどあてにならないものはない、と予てから私は思っていたからです。鑑賞した舞台に好感を持っていなければ手間をかけてアンケートなど書くわけもないのです。少しでも不満を感じたらアンケートに協力するとは私には思えません。評論家をしていた頃。観客からのアンケートはDMの住所を収集するという重要なツールではあったのですが、90年代も半ばを過ぎる頃になると社会が「個人情報」にナーバスになって住所も氏名も書いていない只の紙切れになります。それでもアンケートは入場時に配布されていましたが、綴じられたアンケートは楽屋で回し読みされて出演者が一喜一憂するだけのものに成り下がっていました。それでもライクヘルドが考えたような、顧客満足の機会を提供し続けることでロイヤルティの高い顧客を生むことはあります。劇団や劇場との「特別なつながり」を醸成することは稀にはあります。その集積が「会員制度」、「支持会・後援会」を整える基盤となる亊例です。ただ、そのような鑑賞者の基盤をライクヘルドの定義する「アンバサダー効果」という次のステップに踏み込むマーケティング・スキルは芸術団体の側には欠如していると言わざるを得ません。ライクヘルドの定義する「アンバサダー効果」とは、商品サービスやその生産者に好意を持ってくれて愛着と信頼を感じてくれる顧客が、他の潜在顧客への働きかけをする継続客の行動を指します。それは「インフルエンサー・マーケティング」ではないかと思うかもしれませんが、その行動のインセンティブに金銭が絡まないことが絶対の条件です。私が宮城大学教員だった2000年代に入った頃に「カリスマブロガー」という職業が存在していて、商品の宣伝に企業が高い報酬を積んでブログに書き込みをしてもらい売り上げを拡大するステルス・マーケティング盛んに行われていました。「アンバサダー効果」というのは、そのような金銭的なやりとりとは無縁な愛着と信頼に依拠する情報提供と定義して良いでしょう。その「情報」は、口コミ(バズ・マーケティング)のように相手の生活や価値観に合わせてカスタマイズされて発信されますから、きわめて効率の良い伝わり方を実現するのは確かなのですが。
社会的存在としての「人間」にフォーカスしたWell-beingを指標に。
フレデリック・F・ライクヘルドの顧客満足によって継続顧客を創出する考え方は、「顧客ロイヤルティによる価値創造の成長戦略」というミッションステーツメントがあって、ジョン・グッドマンの発見とはフェイズとレベルが大きく異なっています。ただ、そうであっても、「顧客満足」は商品サービスから受ける一時的な幸福感であることからは逃れられません。「顧客満足」はCS(customer satisfaction)と表現されますが、このSatisfactionには満足の他に喜び・達成・実現・納得などの意があります。ただ、「幸福感」(wellbeing)のニュアンスはまったくありません。新著『人間の安全保障としての文化芸術』で私は「人間は『幸福感』(wellbeing)と『快楽』(pleasure)を混同ししまっているのではないでしょうか」と書いています。セグリマン博士の「ポジティブ心理学」の知見では、HappinessとWell-beingを厳密に区別しています。「Happiness」は、感情的で、一瞬しか続かない短い幸福感であり、「Well-being」を身体的、精神的、社会的に良好な状態を持続する幸福感であり、至福の状態」と明確に分けています。「楽しみ」とか「快楽」というPleasureは「感情」であり、「心象」を指しています。たとえば「満足感」は、a feeling of happinessと感情の状態を表す語彙です。それに対して「be 動詞」を使う「wellbeing」は現在形であろうと過去形であろうと命令形であろうと「存在の在り方」を指しします語彙です。一方で満足の意として使用されているsatisfactionは、言うまでもなく「感情」に関わる語彙であって存在の状態をあらわす言葉ではありません。「顧客幸福度」は前提として、この存在(在り方)であることから出発しなければならないと私は考えています。また、「顧客満足度」は、日本では高度成長期の後の主に80年代に入り、価値観の多様化の時代になって、顧客が何を求めているのかが見えにくくなった結果、生産者主権・供給者主権の尺度として用いられるようになった経緯があります。
WYPとの出会いが劇場経営に新しい地平を切り拓いた。
98年にリーズ市のWYPを初訪問して、年間1000回の包摂型コミュニティ・プログラム実施に圧倒されましたが、初訪問の時から不可思議だったのは、何らイベントがないのに午前中から多くの市民で劇場中が賑わっていることでした。正直言って何故なのか皆目見当がつきませんでした。翌々年の2000年に公共劇場関係者、自治体関係者、メセナ関係者でツアーを組成してリーズ市のある北部イングランド、スコットランドの劇場を数か所めぐりました。リーズではWYP(ウエストヨークシャー・プレイハウス 現リーズ・プレイハウス)の高齢者プログラムである水曜日開催の「Heydays」(ヘイデイズ)に重点に置いて、ここだけで2泊3日を費やした旅になりました。ちにみにHeydaysは「輝ける日々」を意味する慣用句です。このプログラムで高齢者たちの作った小物や作品は、半期に一度のバザーで販売して、その売り上げは市内の福祉施設に寄付されていて、その集計はホワイエに貼りだされます。高齢者たちが社会との関わりを実感できるシステムが担保されているのです。また、何としてでもWYPのスクール・ツアリング・カンパニーの活動を日本人に実際に触れてもらいたいとの欲求があって、2002年に札幌・金沢・東京で「子どもたちの明日のために」のタイトルでNPO舞台芸術環境フォーラムによって開催しました。2000年にWYPに行った際にスクール・ツアリング・カンパニーの演出家ゲイル・マッキンタイアに構想を話して、一昨年亡くなった臼井幹代さんに劇場との折衝を委ねてもらって、私は助成金申請の準備と日本での開催地との交渉に傾注することになります。さいわい 国際交流基金、北海道文化財団、金沢市文化振興財団、トヨタ自動車㈱、アサヒビール㈱から支援を受けることが出来て、当時は関係の深かった札幌市・かでる2・7と金沢市民芸術村からはドラマ工房の場所の提供を、世田谷パブリックシアターは企画意図を共有して貸館料金を支払うかたちで実施できました。英国からツアリングカンパニーの俳優2名、ステージマネージャー1名、シンポジュウムのパネルとして英国芸術評議会の地方組織ウエストミッドランド地域芸術評議会の副議長でアーツコンサルタントのリー・コナー、WYPのアーツ・デベロップメント部長サム・パーキンス、スクール・ツアリング・カンパニー総責任者で演出家のゲイル・マッキンタイア、国内からは中川幾郎氏、高比良正司氏、西田豊子氏、羽下大信氏、川口潤一氏を各氏との日程調整をして各会場に割り振りました。この頃までは、宮城大学・大学院の教師だったこともあって経営者の目線ではなく、通年で包摂型プログラムをほぼ毎日実施しているWYPの、当時の日本では想像を絶する経営を日本に紹介して、劇場それ自体の持っている社会性とそのポテンシャルを認知してもらおうというのが唯一の使命だったと思います。
舞台芸術環境フォーラムでのロジックの進化とアンソニー・ギデンズとの邂逅。
この催しの3月15日から24日という強行スケジュールのあいだに、英国から招聘した講師の誰だったかは不明ですが、英国の社会学者であり、新自由主義を英国に導入したマーガレット・サッチャーによって英国社会に深刻な爪痕を残した負の影響を復旧するためにブレア政権のブレーンを務めたアンソニー・ギデンズのことを耳にしました。強行軍のツアーが終わり、英国からのゲストを見送ってすぐに私はギデンズの『第三の道――効率と公正の新たな同盟』を取り寄せ、彼に関する記事を検索しまくりました。彼は「第三の道の政治が目指すところを一言で要約すれば、グローバリゼーション、個人生活の変貌、自然と人間との関わり等々、私たちが直面する大きな変化の中で、市民一人ひとりが自ら道を切りひらいていく試みを支援することに他ならない」といささか簡略に、しかも楽天的に述べていますが、私に刺さったのは「ウェルフェアとは、もともと経済的な概念ではなく、満足すべき生活状態を表す心理的な概念である。したがって、経済的給付や優遇措置だけではウェルフェアは達成できない」、「福祉のための諸制度は、経済的ベネフィットだけでなく、心理的なベネフィットを増進することも心がけなければならない」でした。(太字筆者)憲法25条に基づいているのは建前としての福祉ではなく、その行間を読み込めば、まさしく「心理的なベネフィットを増進する」が最も重要であり、そのためにこそ「つながりの貧困」を回避する手段を講じなければならないと私は考えました。アーラの館長に就任した当初にはあまり講演依頼はなかったのですが、それでもその頃のPPには「激しい社会の変容に対する『処方箋』としての文化芸術及び劇場音楽堂等の公共的役割」のシートが組み込まれていて、アンソニー・ギデンズの「ポジティブ・ウェルフェアの再評価」が設けられています。彼の「ポジティブ・ウェルフェア」には強い影響を受けました。
そのシートの下には
「孤立しがちな人々の生きる意欲を醸成して、そのポテンシャルを社会の発展に反映させる仕組み=「社会包摂」による誰も排除しない全員参加の共生社会へ。
⇒「公共財及び社会的共通資本」として文化芸術・劇場音楽堂等の位置づけ。
⇒劇場音楽堂等をWell‐ Being (幸福・健康)とWelfare(人生を良き旅に)
のための政策と位置づけて「社会的処方箋」の総合的社会政策拠点に。」
との無謀にも仰々しく政策提案が記されていました。
「子どもたちの明日のために2002」に続けて、2005年には第3回国際劇場経営セミナー&シンポジュウムとして『集客から創客へ-IT社会とアーツマーケティング、その可能性』を国際交流基金、セゾン文化財団、大和日英基金、グレートブリテンササカワ財団の支援で開催しました。タイトルに明示したように、社会的・利他的・公共的価値を梃子にする94年に提起した「創客」のマーケティングに、WYPを精神のランドマークとする愛好者に限定しない新しいマーケット創造(トランスフォーメーション)が起きていたのではないか、との仮説にようやく辿り着けたのがこの頃だったと想い起こしています。少なくとも「創客」への確信はしっかりと私の裡では根をはっていました。ウェルフェアは、日本では弱者救済の意で用いられることが一般的ですが、ギデンスから邦訳すれば福祉を意味するWelfareは「一生を良き旅路にする」との人間の存在に関わる言葉であるとの啓示をうけます。英国の劇場関係者には労働党支持者が多いこともあって、私の日頃の言動や主張から察して、ギデンスの存在を耳に入れたのかも知れません。この時に同時に「Well-being」という語彙を知ります。それがWHO(世界保健機関)憲章前文の「健康の定義」を起草した創立者の一人であるスーミン・スーによって書き込まれた言葉です。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。)
次にWell-beingを仕事に関係する語彙として意識するのは、冨田成輝可児市長から「岐阜医療科学大学の演習に県立東濃高校で実施してるワークショップを使えないか」との相談を受けて、その可能性を探っている時のことです。看護師と薬剤師という医師とは別の視点で患者と、ある意味で異なる立場から関わる医療従事者を育成する意味を見出さなければと考えてWHOの「健康の定義」を頭の隅から引っ張り出しました。そこで「social well-being」を深掘りすることになります。Well-being自体が、それだけで必要十分条件として「他者」が想定されているにもかかわらず、あえてsocialと強調している背景を知りたいと思いました。ここからはあくまでも私の実体験と想像でしかないのですが、岐阜医療科学大学の半期のカリキュラムと講師を決めながら上記の「健康の定義」を読んで、私の裡に小学校低学年の仲の良かった級友の家に遊びに行った時の嫌な記憶がいきなり蘇ってきました。階段の下の納戸のような部屋とは言えない場所を指さして「ばあちゃんが寝ている」との呟きを聞いた気まずさです。
「社会的にも、すべてが 満たされた状態」とは、家族はもちろんのこと、近所との関係性、自尊感情を持った記憶のある古い友人関係等々、それらの他者とのリレーションシップが良好であればあるほど、病気を治そうという「生きる意欲」が内側から湧いてくるのは人間の摂理です。そのために文化芸術の持っている協働性、それによって生じる共創する価値と利他性を活用することは医療に有効であろうと思われました。まさしく多様な「つながり」によってwell-beingの状態に患者の心を誘導して、生きようとする意欲を喚起するスキルを医療現場にはとても必要と考えました。そして、岐阜医療科学大学のカリキャラムに、アーラでの実績のあるコミュニティ・アーツワーカーによる演習が位置づけられて、現在も続いているのです。
そのような中で2021年3月をもって館長を辞することになり、その後3ヶ年は月1回か2回館長ゼミを引き継いで衛ゼミをすることになりますが、私の裡ではアーラの「社会包摂型劇場経営の進化」が止まって、何とはなく「踊り場」になっているという感じを引きづっていました。すなわちアーラのブランドの進化を実感できなくなっていました。コロナ禍と大規模改修が重なって、職員の士気に強い影響を与えたことは否定できませんが、アーラと可児市を一応はナショナルブランドにした「社会包摂型劇場経営」を「創客経営」にさかのぼって一度洗い出してリブランディングする必要を強く感じていたので、館長退職後のゼミで「経営の見直し」を何回か議題にしました。就任時に「創客」を因数分解して芸術愛好者に限定しない劇場経営にシフトしたことは、シュンペーターが、1912年に発表した『経済発展の理論』の中で「新結合」(new combination)という言葉を使って「イノベーション」の概念を提唱していたことか背中を押しました。文化政策用語と社会政策用語を結合させたことまでは間違っていないとの確信は持っていました。しかし、2010年あたりまでは、その話を業界人とすると「そんなのありえない」がほぼ100%の反応でした。生きづらさを感じている市民の生活の中に文化芸術のコミュニケーションスキルで「つながりの構築」を企図することも間違っていなかったと総括は出来ました。最後に残った棘は、「社会包摂型劇場経営は手段」との認識が欠落していたのではないだろうか、という深い自省でした。コロナ禍後の観客の戻りが思わしくない劇場・芸術団体が多くあるのに、コロナが終息した2023年に職員に顧客データを調べさせたところ、驚異的な短期間で客席稼働率はコロナ以前に回復していました。報告を受けて正直これには驚きました。これは、サッチャー政権後の劇場・音楽ホール・美術館の鑑賞者激減という経営環境劣化からWYPが例外的にいち早く回復した事実と同様の立ち直りの速さと思いました。98年の初訪問から幾度となく目撃してたWYPのあの「にぎわい」と「急速な回復」とのあいだに何らかの連鎖と整合性があるのではとの仮説命題に行き着きました。その命題を解くことが、アーラの抱えている「踊り場」を次のフェイズに昇華させる鍵になるのではと考えました。
社会包摂経営は「手段」、着地点はマーケット・トランスメーションとプラットフォーム。
98年のリーズ市初訪問の際に目撃したWYPのあれほどの「にぎわい」は、いま思えば当時の日本人である私の常識では、到底解けない難題だったと思います。観たい芝居、好きな出演者の演技を目撃したいという市民たちが集まっていると考えるのが普通であり、常識だったのですが、毎年のようにWYPを訪れて市民の皆さんの様子を観察していると、明らかにそれとは違った来集軸で多くの市民がWYPを訪れていることが窺がえました。当時のWYPはエントランスを入ると正面に数段の階段があって、それを数段登ると私たちがレストランと呼んでいたテーブルと椅子を自由に移動できて必要に応じて人数分のスペースをつくれる250人程度は入れる広いフリースペースの「フロントルームカフェ」となります。ここはHeydaysのメイン会場としても活用されていますが、プレイハウスキッチンがありフードサービスとドリンクサービス、さらにはプレイハウスバーも併設されています。営業時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時まで、または公演のある日は公演が始まるまでで、そこは午前中から夕方まで多くの市民たちで賑わっています。待ち合わせて会話を楽しむ市民や、コミュニティの小さな集まりなどに利用されていました。何よりもその人々がリラックスしていて、文字通りの「フリースペース」なのです。鑑賞という明確な目的を持って訪れてはいないのです。これは、まったくフェイズの違う来集軸があると確信しました。「欧米には劇場通いの習慣があるから」と2000年代に入っても「日本とは違う」という意味の根拠の薄い羨望を口にする関係者は少なくなかったと記憶しています。それが「隣の芝生」の類のものであることはすぐに分かりました。劇場の後方席から舞台を観ていると、髪の色のせいで客席が明るいのです。「年間1000回のコミュニティ・プログラムに20万人の市民がアクセス」と聞いていて、その事実に実際に立ち会うことで、彼の地の劇場関係者の地道な活動が市民に与えている心理的影響が、鑑賞目的ではない大勢のシアターゴーアーを生み出していると結論づけるしかないと思いました。つまり、WYPの包摂型コミュニティ・プログラムは「手段」であって、その先に潜在顧客の掘り起こしを企図しているのではないかと、私はあの不可思議な「にぎわい」の理由に行き当たりました。三々五々、寄り集まってくつろいで談笑する様子や、テーブルと椅子をアレンジして8、9人のグループが笑みを交えて討議していて、心理的安全性が担保されている穏やかで自由闊達な会議の様など、「負担」「重荷」「好意」を共有するコミュニティが此処にはあるのではないか、との推論に至りました。社会包摂型のコミュニティ・プログラムは、あくまでも「手段」なのではないか、という自問が芽生えました。
WYPの賑わいを理解できない旧態依然としたマーケティング理解の限界。
フィリップ・コトラーが2010年にマーケティング3.0を提唱して「マーケティングはより良い世界をつくる」(Marketing is world better)こそが「マーケットの本質的機能」との認識を提起しました。これを深いところで理解していた現役マーケッターはほとんどいないのではと私は訝しく思っています。いまに始まったわけではないのですが、最近の経済誌で営業部門とマーケティング部門の連携がうまく機能していないとの課題が浮き彫りになっています。その原因は、「目標やKPIだけでなく、業務で使うツールやデータまでもが部分最適に陥っている」という構造的な問題だと分析されています。近年では米国で開発された利益を生み出す部門の連携を強化させるRevOps(Revenue Operations:レベニューオペレーション)というオペレーションソフトまで販売されるようにまでなっています。マーケティングの本家本元とも言える米国でもレベニュー(利潤Revenue)の最大化を唯一無二の到達目標にしているために組織内各機関が機能不全に陥っているようです。この機能不全は、推測でしかないのですが、おそらく日本で著しいと考えています。それには、1950年代初頭に経済団体の視察団が米国に派遣されて「マーケティング」という経営手法が国内企業に導入されたのですが、その時代は米国の消費社会がガルブレイスの『ゆたかな社会』に詳しく書かれているような、いわゆるGolden Ageであり、帰国後に設けられたのは大半が販売促進部署でありセールスプロモーションを所掌する部署でした。「マーケティング=広報宣伝」との理解が一般的になってしまったのです。私は一貫して「マーケティングとは、『売る』ことではなく『売れる環境をつくること』と言い続けて来ました。現在もそれをマーケティングの心柱であり要諦としています。視察団が派遣された当時の米国は、移民の急増と合計特殊出生率が戦前から2を超えて、1947年に3.27と飛躍的に伸びて64年まで3超を継続して、マスメディアの進展と相まって、「依存効果」が大きな影響を社会にもたらして旺盛な消費欲が喚起され、大量生産大量消費による「黄金時代」が築かれた時期です。日本では、そもそもこの最初のボタンの掛け違いが、日本の「マーケティング理解」にとっての不幸の始まりでした。マーケティングの「数量信仰」をブランディングよりはるかに優先上位に置いてしまう勘違いの原点が此処にあります。高度成長期の大量消費時代にDNAとして埋め込まれた「収益の最大化」を求めるマーケッターの習性がほとんど病的になっていると私が判断するのは、人口統計的データであるデモグラフィック・テータに加えて、心理的な傾向を表すライフスタイル、パーソナリティー、社会的階層、価値観、購買動機などまでを収集したビックデータをデータマイニング解析にかけて潜在顧客を抽出してマーケティングに活用しようというシステムか最新の手法として喧伝されていることです。そして、必ず個人情報保護法に抵触しないようにとの但し書きが付与されている異常さに、私は辟易としています。「パーソナライズド・マーケティング」がそれです。2012年年4月の「ハーバード・ビジネスレビュー」では、ビッグデータはどんなにわかりやすく分析されたとしても、大きな決断(ビッグディシジョン)による意思決定はマーケッター自身によって補完されなければならないとされています。ここまで来てしまうと、まぎれもなく「生産者主権」をより強固に推し進めようとの意志を感ぜざるを得ません。そもそも「顧客満足度」は、価値観の多様化で顧客が見えなくなった生産者が、「見える化」を企図したものでしかないと私は思い続けて来ました。自分たちの営業企画や経営企画を確認して誤謬はなかったことを確認するツールでしかなかったのです。この水準では、WYPの不可思議とも思える「にぎわい」がなぜ起きているのかを解析できるはずがありません。せいぜい広報宣伝が的確でうまくいっているので多くのチケットが売り捌けたからだろう程度の分析にとどまってとしまうだろうと思います。
CSV経営というBeyond GDPへの歴史的な大転換。
ハーバード・ビジネススクールのマイケル・ポーター教授は、競争優位の企業戦略の大家であり、企業経営者にとってはレジェンド的な存在でした。私の周囲にも崇拝者と思われる人物が何人もいました。ポーターの競争戦略は、「コストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」「集中戦略の3つ基本戦略からなっており、その最適化によって利潤の最大化をアウトプットすることで競争優位の持続継続性をキープするというもので、宮城大学の教員時代にも、学部生・院生を問わずゼミ生の中にはポーター崇拝者は少なからず見受けました。その彼が社会貢献コンサルタントのマイク・クラマーとの共著の論文を2006年の「ハーバート・ビジネスレビュー」に発表します。その論文である『Strategy and Society(競争優位のCSR戦略)』は、CSRは数少ない最適解のひとつと考えていました。ただ、「現行のCSRはボランティア派遣や寄付金の拠出」を専らとして社会的責任を担保するために収益の一部を流出しているに過ぎない」のでもっと戦略化しなければ、というもので、あまりポーターの学績と生き方を好ましく思っていなかった私にはいささか肩透かしを食らった論文内容でした。当時の私はコーポレイト・ソーシャルレスポンシビリティ(CSR企業の社会的責任:経営)に強い関心と、強欲資本主義の申し子のような企業経営者や自分の専門分野であるマーケティングにおいても新自由主義の時流下で、勝ち馬に乗って勘違いしているマーケッターばかりで嫌気がさしていた時代でした。
アーラの館長になって打ち出した「社会包摂型劇場経営」も、WYPで目の当たりにした包摂型の経営の影響から、館長に招聘する話の出た2006年当初はCSRとして展開する心積もりでした。しかし、「あいつはまた妙なことを始めたな」くらいの業界の反応でした。シュンペーターの「新結合=イノベーション」など業界では理解不能だったのでしょう。アーラの「社会包摂型経営」が当初は受け入れられなかったのは、「社会貢献事業」は利益が出てはじめてやるものとの「常識」が頑迷にあったです。その「常識」を発想の逆転で陳腐化させたのが、2011年の『Creating Shared Value(共創価値創造の戦略)』でした。従来は「芸術的価値」と「社会的価値」はトレードオフ(二律背反)とされている「常識」からテイクオフして、経済利益と社会課題の解決を自社の製品サービスで一体的にともに追求するのが企業組織の存在価値であり、その相乗効果を生み出すべきとの知見が示されたのです。まさしくシュンペーターの「新結合」によるイノベーションでした。その3年後にはフィリップ・コトラーの『マーケティング4.0』が刊行されて、3.0の「人間中心のマーケティング」をさらにバージョンアップさせて、共創共感共有のつながりによるADVOCATE(周りに勧める)までを視野を拡張させたマーケティング概念を提唱して企業組織の経営哲学の大転換期を誘発生成しました。「芸術的価値」のみならず、「社会的価値」とあわせての相乗効果で「経済的価値」をも健全に生み出す経営と経営者こそが、2000年代に入った直後にもてはやされたコストカッターでしかない「プロの経営者」と比べて、まぎれもなく「体温のある人間的な経営者」なのではないでしょうか。Beyond GDPの時代の趨勢から言っても、また文化芸術に関わる者としても、さらには公立文化施設で公共的使命を果たすことを使命とする者としても、私は館長就任以来、体温のある経営者でありたいと思い続けていましたし、理解不能と思われたWYPの賑わいの理由を解く糸口にたどりつけそうとの思いを持てるようになりました。
Ethical human relationshipでつながるソリューション・プラットフォーム(SP)、「顧客幸福度」がマーケティングを変革する。
98年の初訪問から幾度となく目撃してたWYPのあの当時の日本では到底思いつかない「にぎわい」と、サッチャー政権下での中間層の没落による鑑賞者の激減からのWYPの「急速な回復」とのあいだに何らかの連鎖と整合性があるのではとの仮説命題に行き着きました。縷々述べてきたような時代環境の激変とも言える地滑り的な転換を前にして、ともかくもWYPの「にぎわい」を私はマーケット基盤の頑強さにあるのではと当初は考えていました。少なくとも新著を書いている段階までは年間1000回実施しているコミュニティ・プログラムがそのマーケットを下支えしていて『人間の安全保障としての文化芸術』では「新しいマーケット」をつくる必要性を考えていました。文化政策部会の人口減少に対する政策提案である「マーケットイン」は大衆に媚びることとして、芸文振運営委員会で臨席していた文化庁職員を厳しく批判し、激しく叱責しました。後日、「マーケットイン」の不用意きわまる語彙は文化政策部会の文言から削除されていました。マーケットインでは何ら対策の役割を果たせないからです。1950年代の米国での「リージョナルシアター運動」の嚆矢となったのが、演劇に対する価値観がブロードウェイ一のマーケットインによる製作姿勢に一極化することへ危機意識を持ったのが若い演劇人とニューヨーク大学演劇科の学生たちで、そのムーブメントの担い手だったのですが、私は時間を超えて彼らの志と共鳴していました。
あのWYPの賑わいを理解するためには、「マーケティング」それ自体のコペルニクス的な転換を語らなければいけないだろうと私は考えています。それは同時に、「顧客満足度」から「顧客幸福度」への緩やかな推移がなぜ起きているのかを明らかにすることでもあります。端的に言えば大量生産大量消費時代の「マスマーケティング」から個客とのつながりへの道標である「ONE to ONE」への転位なのですが、とは言ってもマスマーケッティングが失速失効している訳ではありません。前述した「パーソナライズド・マーケティング」は、ほとんど病的と思える数量信仰に憑りつかれたマーケッターによるマスマーケティングの延命のための窮余の一策でしかないと思っています。これは、既に記しましたが、最新のマーケティング理論では、コトラーの最新刊『コトラーのH2H(ヒューマン・トゥ・ヒューマン)人間中心のマーケティング』では、「価値の共同生産性」の範囲が「C with C」にまで拡張しています。顧客相互のあいだで「価値の共創」が行われるということです。これは、『Creating Shared Value(共創価値創造の戦略)』でマイケル・ポーター&マイク・クラマーによって提唱されたCSV経営とほとんど符合します。この生産者主権のマーケティングに揺らぎが生じ始めたのは、ドン・ペッパーズとマーサ・ロジャースの『The One to One Future』(ワン・トゥ・ワンの未来:顧客一人ひとりと関係を築く)によって提唱された1993年だと私は思っています。これが日本では、『ワン トゥ ワンマーケティング』として2年後に出版されます。日経新聞の連載コラム「やさしい経済学」でマーケティングのおもしろさに触れて、この先生なら私を正しく先導していただけるとお訪ねして私淑していた、当時は慶應義塾大学に在籍しておられた井関正明先生が監訳者としてこの出版に関わっていて、その縁で出版直後に紀伊国屋書店で購入してむさぼり読んだ記憶があります。「ONE to ONE」は、消費者ひとりひとりの購買傾向からニーズを読み取り、個々に対して最適なコミュニケーションを行うマーケティング活動と概念規定されます。90年代はじめに岡谷市の離風霊船合宿の時にインスパイアを受けた「関係づくりマーケティング」とそれは重なっていました。
「ONE to ONE」は、当時としては未来概念でしたが、90年代に入って、PCの普及とインターネットのコモディティ化によって、比較的大容量の顧客データベース作成が可能となって、急速にリアルなフェイズでのマーケティング手法となりました。井関先生が事有る毎に唱えていらして、私の研究の心柱となる関係づくりのマーケティング、すなわち「マーケティング」の基本的基盤であるリレーションシップ・マーケティングが、迷宮迷路に入り込んで出口の見えないマスマーケティングの対立概念として登場した嚆矢だったと振り返ります。フリップ・コトラーの最新刊『Human to Human Marketing』の冒頭部分で、「利益至上主義のマーケッターの行き過ぎた非倫理的行動により、(中略)マーケティングのイメージは近年悪化の一途を辿っている。大半の人は『マーケティング』」と聞くと、『嘘』『欺瞞』『ごまかし』『迷惑』『操作的』といったネガティブな言葉を連想する」と数量信仰に呪縛されたマスマーケティングにしがみつくマーケッターを舌鋒鋭く批判しています。マーケティング3.0で、コトラーはマーケティングの本質が「つながりの構築」であり、リレーションシップ・マーケティングにあると見通していると明確に確信しましたが、1971年の副題に「行動変革のための戦略」と記した『ソーシャル・マーケティング』の日本語版(1995)の序文でも、利潤最大化を目指した営利目的のマネジリアル・マーケティングが倫理性を欠いて世界に変調を来たし、マーケティングが担ってきた「物質的な進歩の増大が、かえってさまざまな社会的問題を生み出し、悪化させてきた」との現状認識と危機意識と自省を記しています。それほど「数量信仰」のしみついたマスマーケティングの頑迷固陋さはしたたかなのです。マスマーケティングに肝要な指標と「顧客満足度」による経営判断の正当性が信じられていたビジネス環境と、マーケットシェアよりも生涯価値(Lifetime Value)重視の継続客による生涯支出に価値を見出すマーケット・イノベーション、そのベースとなるリレーションシップ・マーケティング再評価が浮上してからおよそ30年を経て、いま、「顧客幸福度」こそが「消費者主権のビジネス指標」ではないかとの議論が登場してきています。非常に長い端境期ではありますが、これは何を意味するのでしょうか。
セグリマン博士の「ポジティブ心理学」の知見を敷衍すれば、「顧客満足度」は感情的で、一瞬しか続かない短い幸福感(happiness)であり、「顧客幸福度」は、身体的、精神的、社会的に良好な状態を持続する幸福感(well-being)であり、いわば生き方をみずから選択する消費の在り方と定義できます。さらに「顧客満足度」は提供される製品サービスの課題解決度に関わる幸福感であり、「顧客幸福度」は、提供する主体(事業体・企業・組織)への消費者の評と言えるのではないでしょうか。さらに、既に述べたように、「be 動詞」を使う「wellbeing」は現在形であろうと過去形であろうと命令形であろうと存在の「在り方」を指す語彙です。さらに発展させれば、その事業体(企業組織)の社会的存在価値の論証たりうるエビデンスとなるとも言えます。社会状況の変化によって、一時的な幸福感よりも、生き方や社会的存在としての幸福感への欲求の高まりが、「顧客幸福度」という指標の登場環境を用意したのではないでしょうか。つまり、CSV経営、ESG経営、パーパス経営等の事業体の社会的信頼による持続継続性を担保する重要な基盤ファクターになったと考えられます。『「地球幸福指数」とポジティブ心理学の知見』の項で挙げたセグリマン教授による幸福度を上げる5つのポイントを消費者である市民の立場から私流に書体を換えて示してみます。
- つながる(Be Connect):何らかのコミュニティの一員として受け容れられる。
- アクティブになる(Be active):生活実感から日々の生活を考えて行動できる。
- 好奇心を持つ(Take notice):環境や社会の変化に好奇心をもって参加し行動する。
- 学び続ける(Keep learning):保守的にならず新しい考え方に触れることを喜びとする。
- 与える(Give):利他的な生活態度が究極には自分に利するとの姿勢で生活する。
如何でしょうか。さらに、下記に示すように自由意志で生き方を選択することも「幸福度」を持つためには必須であると、私は考えます。
- 自己選択(Make a choice own will):自己意志で有意に選択する。
コロナ禍にヨーロッパの知性と称されるジャック・アタリが芸術文化産業に対して発した「Vital Industry」(生命維持装置としての産業)という評価にそってセグリマン教授の5つのポイントを加筆してみました。劇場音楽堂と芸術団体は、世界的な人間を取り囲む危機的な環境変化を前にして、アジャイル・マインドセット(柔軟思考)による新たな発想とデザイン思考が強く求められているのだと私は思います。
ここで「欧米は劇場通いの習慣があるから」という引かれ者の小唄を思い出しました。WYPの午前中からの「にぎわい」は、心理的安全性と社会と他者とのつながりを実感できる「心のランドマーク」へのリーズ市民に習慣化した結果なのではないでしょうか。WYPの賑わいはWell-beingの保障された空間への誘客効果による現象で、それは市場のように経済行為の伴わない、いわば「つながりのプラットフォーム」から受け取る「報酬」への期待があるからなのではないか、との仮説命題の解が垣間見えて来ました。新著では、マーケットが金銭的な多寡によって成立するだけではなく、近年では社会心理的な価値も加味された取り引きに変化してきているのではという仮説を書いています。習慣と言えば、おそらく西欧人の「教会通い」に似た心理に通底するとも考えました。ここでは詳しくは論じませんが、臨床心理学分野には「教会」と「習慣化」の知見があり、「教会に行くとき、何かをするという『doing』的なものだけではなく、神様の前に静まる『being』的な姿勢が大切と説いています。生き方や存在に関わる「習慣化」です。ここまで来ての現時点での結論は、リーズ市民の「精神のランドマーク」としてWYPという劇場が市民のプラットフォームのように存在していて、あの「にぎわい」の現況が生まれていると私は考えています。当然ですが、それによって潜在顧客の顕在化(掘り起こし)として機能しています。その機能が「顧客幸福度」によっているのは言うまでもないことです。年間1000の包摂型コミュニティ・プログラムの先にソリューション・プラットフォーム(SP)の実現という社会的価値の実現を構想できるかが肝要なのです。幸せな人は創造性が3倍、生産性が1.3倍高いというデータもあります。プレイハウスの劇場職員が喜びに満ちて、いきいきと仕事に従事している理由もここにあるのではと思っています。